最近の夫婦を扱った小説は、地味に面白い。特に最近の傾向なのかもしれないが、自己批判的「妻」批判がすごい、と私は思う。そのすごさは、とても地味でわかりにくいけれども、「妻」という存在の仕方のドン詰まり感を余すところなく書いているところに現れている。
川上弘美の『風花』にしろ井上荒野の『切羽へ』にしろ、主人公の「妻」は弱者だ。いわゆる「女、子供」という言い方に典型的に現れるような弱者であり、そういう「私、感傷的で、弱いんです、天然の生き物なんです、守って下さい」という女性像を女性作家がわざわざ書いて見せているところに、女性による地味な非-フェミニズム(古いフェミニズムにとってかわるもう一つのフェミニズムかもしれないが)みたいなものを感じる。
例えば、『風花』が夫に裏切られた妻による自立の物語だったらあんまり面白くない。結婚という制度はそもそもどこか変だ、というありきたりな違和感しか残さない。しかし、逆に、夫婦の純愛物語として読めるかというと、読めなくはないけれどそう言ったら台無しという気がする。少なくとも、これは「雨降って地固まる」んではなく(主人公の親の世代の話ならそういう話になったと暗示させるエピソードがある)、雨降ったら地が溶けてしまうのが、昨今の「妻」物語なのだ。
雨が降ったら「妻」というあり方はすぐにも溶けてなくなるのだが、『風花』の主人公は、なかなか自立を選択しない。かといって、元の鞘にももどらない。「元の鞘」なんてものはもともとなかったのかもしれないなどと考えあぐねながら、ずっとぐちゃぐちゃした地面を歩き続けるのである。
そういう脈絡で読むと、『風花』のラストは、地味だが強烈で、納得させるものがあった。「地味だけど強烈」と言うと、相反するものの特徴が共存しているという印象だが、この小説が描く「妻 のゆり」は、ほんとに地味にして強烈な感じがする。まず、非常にいらいらさせられる。しかし、いらいらするのは、こっちのせいであって、「のゆり」のせいではない。「のゆり」の「のゆりらしさ」にいらいらするのは、多分私の方に原因があるのだろう。だって、「のゆり」の個性は本当に野に咲く天然の百合のようにただ咲いているわけなんだから。そして、そういう「のゆりらしさ」を守って来たのは、ひとえに「夫 卓哉」との結婚に他ならないことは容易に察しがつく。
そういう意味で、この小説の「夫 卓哉」像は、なかなか奥が深い。夫 卓哉は、結婚生活を「どこにもない美しい山に登る」イメージで始めた人物で、そのせいか不思議な仮面をかぶっている。その仮面を脱がせようという奮闘努力が、「のゆり」の愛の物語になっていくわけである。しかしこの愛の物語が、ハッピーエンドかと言うと、一言では言いあらわせないようになっていて、流石である。
けっこう切ない、「やりきれない」ラストだったと思う。それは、やっぱり、作家自身の、どこか身を痛めるような「結婚」批判の成果だからだと思う。
川上弘美の『風花』にしろ井上荒野の『切羽へ』にしろ、主人公の「妻」は弱者だ。いわゆる「女、子供」という言い方に典型的に現れるような弱者であり、そういう「私、感傷的で、弱いんです、天然の生き物なんです、守って下さい」という女性像を女性作家がわざわざ書いて見せているところに、女性による地味な非-フェミニズム(古いフェミニズムにとってかわるもう一つのフェミニズムかもしれないが)みたいなものを感じる。
例えば、『風花』が夫に裏切られた妻による自立の物語だったらあんまり面白くない。結婚という制度はそもそもどこか変だ、というありきたりな違和感しか残さない。しかし、逆に、夫婦の純愛物語として読めるかというと、読めなくはないけれどそう言ったら台無しという気がする。少なくとも、これは「雨降って地固まる」んではなく(主人公の親の世代の話ならそういう話になったと暗示させるエピソードがある)、雨降ったら地が溶けてしまうのが、昨今の「妻」物語なのだ。
雨が降ったら「妻」というあり方はすぐにも溶けてなくなるのだが、『風花』の主人公は、なかなか自立を選択しない。かといって、元の鞘にももどらない。「元の鞘」なんてものはもともとなかったのかもしれないなどと考えあぐねながら、ずっとぐちゃぐちゃした地面を歩き続けるのである。
そういう脈絡で読むと、『風花』のラストは、地味だが強烈で、納得させるものがあった。「地味だけど強烈」と言うと、相反するものの特徴が共存しているという印象だが、この小説が描く「妻 のゆり」は、ほんとに地味にして強烈な感じがする。まず、非常にいらいらさせられる。しかし、いらいらするのは、こっちのせいであって、「のゆり」のせいではない。「のゆり」の「のゆりらしさ」にいらいらするのは、多分私の方に原因があるのだろう。だって、「のゆり」の個性は本当に野に咲く天然の百合のようにただ咲いているわけなんだから。そして、そういう「のゆりらしさ」を守って来たのは、ひとえに「夫 卓哉」との結婚に他ならないことは容易に察しがつく。
そういう意味で、この小説の「夫 卓哉」像は、なかなか奥が深い。夫 卓哉は、結婚生活を「どこにもない美しい山に登る」イメージで始めた人物で、そのせいか不思議な仮面をかぶっている。その仮面を脱がせようという奮闘努力が、「のゆり」の愛の物語になっていくわけである。しかしこの愛の物語が、ハッピーエンドかと言うと、一言では言いあらわせないようになっていて、流石である。
けっこう切ない、「やりきれない」ラストだったと思う。それは、やっぱり、作家自身の、どこか身を痛めるような「結婚」批判の成果だからだと思う。

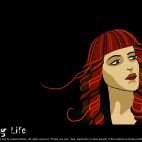
コメント