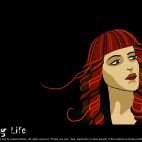ここ一ヶ月か二ヶ月か、ずっと中国茶が飲みたいと思っていた。もちろん、手近なところでウーロン茶とかジャスミン茶の茶葉でも買ってくればよさそうなものだが、茶盤の上に茶壷をおいて、大きなお湯さしで上からじゃばじゃばお湯を注いで飲む中国茶が飲みたいのである。
よく渋谷で映画を見た後などは、道玄坂途中の脇道にある中国茶専門店の三階に登って、茶道具を使って、いつまでもお茶を飲んでいる。それを最後にしたのは、今年はじめ頃だった。そのときは、店の階段途中に、アイドルグループが取材に来たときの記事や写真が貼ってあって、最初はおやと思っただけだったが、お茶を飲んでいる間に、その記事の中の一人によく似た雰囲気の青年が(といっても別人にちがいないが)かなり年配の女性を連れてやって来て、すごくもってまわったおねだりをするのが気になった。女性の方はしきりに、引っ越し祝いに何が欲しいか聞いているのだが、男の方は、欲しい物はない、お金以外は、と言う。それも、物をプレゼントされるのがいかに苦痛か、本当に趣味に合うものなんてわずかしかないのに、という話を詳しくした上で言う。年配の女性は、でもお金っていやだわ、一緒に何か選びましょう、と言う。すると、男は、突き放したように、それではお気持ちだけで、と言って話をそらす。窓際のすぐ横のテーブルだったので、声がよく聞こえてしまう。塔のてっぺんのすごく居心地のいい店の印象が、そんなことがあって変わってしまった。
それでというわけではないが、今回は、渋谷じゃなくて、横浜中華街の中国茶専門店を目指した。夕刻で、待ち合わせて来た夫は、一通り食べ歩きをしたくて、元町と石川町の間を行ったり来たりした後に、開帝廟通り近くのお目当ての店に入る。木枠の窓が開け放されていて、金魚の絵が書かれた鉢があちこちにおいてあって、なんか懐かしい気持ちになるお店である。メニューを見ているうちに、まだ飲んだことがない白茶の白牡丹が飲みたくなる。これが大正解で、これを飲みなさいと身体が最初から命じていたかのようである。白いお茶と言われるだけに、薄い色だけど、とても豊か、深い新鮮な香り。果実の芯を思わせる苦みがふわっとくる。私は、ボディという言葉が浮かぶほどしっかりした味だと思うけど、夫はさっぱりしていると言う。華奢だけど美人なお茶だと思う。夫も私も鉄観音のような青茶を頼まなかったせいか、茶盤の上でじゃぶじゃぶやったり聞香杯を嗅いだりするための茶道具一式が出てこなかったのはちょっと残念だった。けど、白牡丹の白桃色を鑑賞するにはガラス製の茶器があう。三煎目くらいから、汗が吹き出てくるような感じになって、ちょっとハイ??なってしまう。気に入ったので買って帰って、また夜遅くに飲んだのだった。
よく渋谷で映画を見た後などは、道玄坂途中の脇道にある中国茶専門店の三階に登って、茶道具を使って、いつまでもお茶を飲んでいる。それを最後にしたのは、今年はじめ頃だった。そのときは、店の階段途中に、アイドルグループが取材に来たときの記事や写真が貼ってあって、最初はおやと思っただけだったが、お茶を飲んでいる間に、その記事の中の一人によく似た雰囲気の青年が(といっても別人にちがいないが)かなり年配の女性を連れてやって来て、すごくもってまわったおねだりをするのが気になった。女性の方はしきりに、引っ越し祝いに何が欲しいか聞いているのだが、男の方は、欲しい物はない、お金以外は、と言う。それも、物をプレゼントされるのがいかに苦痛か、本当に趣味に合うものなんてわずかしかないのに、という話を詳しくした上で言う。年配の女性は、でもお金っていやだわ、一緒に何か選びましょう、と言う。すると、男は、突き放したように、それではお気持ちだけで、と言って話をそらす。窓際のすぐ横のテーブルだったので、声がよく聞こえてしまう。塔のてっぺんのすごく居心地のいい店の印象が、そんなことがあって変わってしまった。
それでというわけではないが、今回は、渋谷じゃなくて、横浜中華街の中国茶専門店を目指した。夕刻で、待ち合わせて来た夫は、一通り食べ歩きをしたくて、元町と石川町の間を行ったり来たりした後に、開帝廟通り近くのお目当ての店に入る。木枠の窓が開け放されていて、金魚の絵が書かれた鉢があちこちにおいてあって、なんか懐かしい気持ちになるお店である。メニューを見ているうちに、まだ飲んだことがない白茶の白牡丹が飲みたくなる。これが大正解で、これを飲みなさいと身体が最初から命じていたかのようである。白いお茶と言われるだけに、薄い色だけど、とても豊か、深い新鮮な香り。果実の芯を思わせる苦みがふわっとくる。私は、ボディという言葉が浮かぶほどしっかりした味だと思うけど、夫はさっぱりしていると言う。華奢だけど美人なお茶だと思う。夫も私も鉄観音のような青茶を頼まなかったせいか、茶盤の上でじゃぶじゃぶやったり聞香杯を嗅いだりするための茶道具一式が出てこなかったのはちょっと残念だった。けど、白牡丹の白桃色を鑑賞するにはガラス製の茶器があう。三煎目くらいから、汗が吹き出てくるような感じになって、ちょっとハイ??なってしまう。気に入ったので買って帰って、また夜遅くに飲んだのだった。
黒谷都 松沢香代Ku in ka
2009年5月22日 ポエムはじめて見る本格的な人形劇。でも途中まで人形劇であることを忘れていた。というか、いわゆる人形劇の枠をはるかにこえていて、人形と人間の関係劇を見ているようだった。
ああそうだ、アートって呪術でもあったと思って見ているうちに、本物の「地霊」とか「精霊」をこの目で観てしまったような気さえする。
まず穴ぼこだらけの白い布団が天上から吊るされている。会場が暗くなると、開け放しの窓の外から遠い六本木の喧噪とともにただの夜がやってくる。その夜が、この催しの「幕」なのだ。
以下は見ながら、ひとりでに自分の中で紡がれてしまったストーリー。
穴だらけの毛布は、実は生き物の卵を生み出す白い闇夜で、月の騒々しい干渉でいつの間にかぶつぶつと呪縛を解かれて、お餅みたいなちっちゃいクッションをぶらんぶらん振り回しながら命を吹き込んでいく。それが細胞のように組み合されて、編み込まれて、筒状の闇がお互い呼び交す夜、というような新たな夜の情景へと変化して行く。どこからどう登場したのか思い出せないけれど、闇の杯で出来た馬が仲間を呼び息絶えると、はじめて顔を持つ人形が立ち上がってきて、歌をうたってふざけ始める。そのときはじめて、目の前で布を操っているパフォーマーが人形遣いだったことに思い至る。なんだろう、これって、人形遣が、どうやってものに命を吹き込むのか、その儀式を目にしているのかもしれないと思う。でも、それと同時に、そのすべてが演出であり、人形遣は人形遣の役を演じてもいると気づいて驚く。
日常とは切り離して、アートとして見ているわけだけど、自分の日常にふっとリンクする瞬間があって、それは、今回は、「穴だらけの毛布」を上から吊るしている紐が、パフォーマーたちによって切られたり外されたりする過程で、上から、わーっとたくさんのものが雨霰と降ってくるシーンだった。それらは、ビー玉とかあめ玉のような奇麗な光るものなのだが、演者がびっくりして身をすくませる、というシーン。そのシーンは、「今 ここ」の瞬間に与えられる贈り物について言い表しているという感じがして、はっとした。私も、そのとき、いっぱい与えられて、身をすくませている、という気分になったものだった。今を生きるって難しい。けれど、確かにそれが一番大事だと思う。私の場合、批判的な言説に巻き込まれているとそれが出来ない。
ああそうだ、アートって呪術でもあったと思って見ているうちに、本物の「地霊」とか「精霊」をこの目で観てしまったような気さえする。
まず穴ぼこだらけの白い布団が天上から吊るされている。会場が暗くなると、開け放しの窓の外から遠い六本木の喧噪とともにただの夜がやってくる。その夜が、この催しの「幕」なのだ。
以下は見ながら、ひとりでに自分の中で紡がれてしまったストーリー。
穴だらけの毛布は、実は生き物の卵を生み出す白い闇夜で、月の騒々しい干渉でいつの間にかぶつぶつと呪縛を解かれて、お餅みたいなちっちゃいクッションをぶらんぶらん振り回しながら命を吹き込んでいく。それが細胞のように組み合されて、編み込まれて、筒状の闇がお互い呼び交す夜、というような新たな夜の情景へと変化して行く。どこからどう登場したのか思い出せないけれど、闇の杯で出来た馬が仲間を呼び息絶えると、はじめて顔を持つ人形が立ち上がってきて、歌をうたってふざけ始める。そのときはじめて、目の前で布を操っているパフォーマーが人形遣いだったことに思い至る。なんだろう、これって、人形遣が、どうやってものに命を吹き込むのか、その儀式を目にしているのかもしれないと思う。でも、それと同時に、そのすべてが演出であり、人形遣は人形遣の役を演じてもいると気づいて驚く。
日常とは切り離して、アートとして見ているわけだけど、自分の日常にふっとリンクする瞬間があって、それは、今回は、「穴だらけの毛布」を上から吊るしている紐が、パフォーマーたちによって切られたり外されたりする過程で、上から、わーっとたくさんのものが雨霰と降ってくるシーンだった。それらは、ビー玉とかあめ玉のような奇麗な光るものなのだが、演者がびっくりして身をすくませる、というシーン。そのシーンは、「今 ここ」の瞬間に与えられる贈り物について言い表しているという感じがして、はっとした。私も、そのとき、いっぱい与えられて、身をすくませている、という気分になったものだった。今を生きるって難しい。けれど、確かにそれが一番大事だと思う。私の場合、批判的な言説に巻き込まれているとそれが出来ない。
ルドルフ・シュタイナー『職業のカルマと未来』
2009年5月12日 ポエム西川隆範訳 風濤社
ふとルドルフ・シュタイナーを読みたくなって読んでみた。
きっかけはいろいろ思い当たるけれど、そのひとつは、清志郎が死んでしまって、その魂とか精神はどこにいってしまうのだろう、などと思ったからだ。(それと、これまた、たまたまなのだが、昨日観た演劇『雨の夏、三十人のジュリエットが還って来た』のラストにも、清志郎の曲が流れて、演劇の回収できない何かを洗い流してしまって、それほどに「回収できない何か」の対極である精神とは何か考えさせられてしまった。)
難しい独特な語彙の嵐の中読み進んで、結構納得してしまったのは、実社会には奇妙に感情が抜け落ちていて、そういう傾向はきっと加速するだろうけれど、そういう現実もあながち無意味ではない。それに、そういう現実とは対極のものとして、芸術をはじめとする精神的(超感覚的というべきなのか)なものがある。という、どこかもうすでに知ってはいるけれど、なかなか受け入れられなかったこと。読んだ分量の割に理解できたことは少ないが、読んでいて受け入れる気になって、ちょっと大人になった気がした。もちろん気がしただけだけど。
「ぼくのすきなせんせい〜」と「おとなだろ〜?」の間。
「シュタイナー人智学」という曰く言いがたい飛躍。
ふとルドルフ・シュタイナーを読みたくなって読んでみた。
きっかけはいろいろ思い当たるけれど、そのひとつは、清志郎が死んでしまって、その魂とか精神はどこにいってしまうのだろう、などと思ったからだ。(それと、これまた、たまたまなのだが、昨日観た演劇『雨の夏、三十人のジュリエットが還って来た』のラストにも、清志郎の曲が流れて、演劇の回収できない何かを洗い流してしまって、それほどに「回収できない何か」の対極である精神とは何か考えさせられてしまった。)
難しい独特な語彙の嵐の中読み進んで、結構納得してしまったのは、実社会には奇妙に感情が抜け落ちていて、そういう傾向はきっと加速するだろうけれど、そういう現実もあながち無意味ではない。それに、そういう現実とは対極のものとして、芸術をはじめとする精神的(超感覚的というべきなのか)なものがある。という、どこかもうすでに知ってはいるけれど、なかなか受け入れられなかったこと。読んだ分量の割に理解できたことは少ないが、読んでいて受け入れる気になって、ちょっと大人になった気がした。もちろん気がしただけだけど。
「ぼくのすきなせんせい〜」と「おとなだろ〜?」の間。
「シュタイナー人智学」という曰く言いがたい飛躍。
ジュリエットという純愛について
2009年5月12日 ポエム蜷川幸雄演出『雨の夏、還って来た三十人のジュリエット』を観に行く。
生の上演の中にしかないすべての素晴らしい体験については、今ここで書かない。
今書きとめたいのは、この演劇が書かれたそのモチベーションかもしれない一つについてである。
その一つとは、「純愛」批判のようなもの、である。
どこかおさまりのつかないドラマの結末に関して整理をつけるには、この演劇が書かれるに至った動機を、自分の受けた印象から考えるしかないという気がする。
演劇の中のモチーフになっているシェイクスピアの『ロミオとジュリエット』。ロミオとジュリエットのような純愛が現実にあるとして、その個々の純愛そのものではなくて、このような純愛を至上のものとする志向は、まるで、民族主義や軍国主義のように熱狂的で、なにかとても危うく破滅的である。しかもこの純愛が虚構の枠からでて現実のものとして狂おしく求められる時、すでに、純愛とは、カタルシスの生け贄として捧げられた供物であり、このカタルシスによってエスカレートする欲望は、ひどく暴力的な欲望と化してしまいそうだ。
だから、私も、たぶんドラマの意志も、純愛そのものでなく、「純愛」という言葉ないし概念に違和感を感じる。それは、言葉として括れないものを言葉にして、欲望ないし消費の対象にして、大々的な破壊を行うための装置なのだという気がする。
純愛そのものに関しては、多分に幼く、原始的で、平凡で、感傷的で、しかしまあどうしてか人を感動させるものには違いない。
どういう感動かというと、それは、例えば、シンガーが大きな声で歌っているのを聞くだけで訳もなくジンとする、役者がその存在感だけで心を震撼させる、シェイクスピアの詩が前後の脈絡なく情熱を呼び起こす、といったことに非常に近い感動なのだ。私のなかでは、純愛の葛藤と博愛精神とは見分けがつかないほど表裏一体である。つまり表現者の感動的な博愛精神が、いつも純愛という物語を生み出すのである。しかし、「純愛」消費社会の中に博愛精神はほとんど見いだせない。
そういう現実と精神の乖離というか矛盾は、ドラマのなかで、回収されないままである。
生の上演の中にしかないすべての素晴らしい体験については、今ここで書かない。
今書きとめたいのは、この演劇が書かれたそのモチベーションかもしれない一つについてである。
その一つとは、「純愛」批判のようなもの、である。
どこかおさまりのつかないドラマの結末に関して整理をつけるには、この演劇が書かれるに至った動機を、自分の受けた印象から考えるしかないという気がする。
演劇の中のモチーフになっているシェイクスピアの『ロミオとジュリエット』。ロミオとジュリエットのような純愛が現実にあるとして、その個々の純愛そのものではなくて、このような純愛を至上のものとする志向は、まるで、民族主義や軍国主義のように熱狂的で、なにかとても危うく破滅的である。しかもこの純愛が虚構の枠からでて現実のものとして狂おしく求められる時、すでに、純愛とは、カタルシスの生け贄として捧げられた供物であり、このカタルシスによってエスカレートする欲望は、ひどく暴力的な欲望と化してしまいそうだ。
だから、私も、たぶんドラマの意志も、純愛そのものでなく、「純愛」という言葉ないし概念に違和感を感じる。それは、言葉として括れないものを言葉にして、欲望ないし消費の対象にして、大々的な破壊を行うための装置なのだという気がする。
純愛そのものに関しては、多分に幼く、原始的で、平凡で、感傷的で、しかしまあどうしてか人を感動させるものには違いない。
どういう感動かというと、それは、例えば、シンガーが大きな声で歌っているのを聞くだけで訳もなくジンとする、役者がその存在感だけで心を震撼させる、シェイクスピアの詩が前後の脈絡なく情熱を呼び起こす、といったことに非常に近い感動なのだ。私のなかでは、純愛の葛藤と博愛精神とは見分けがつかないほど表裏一体である。つまり表現者の感動的な博愛精神が、いつも純愛という物語を生み出すのである。しかし、「純愛」消費社会の中に博愛精神はほとんど見いだせない。
そういう現実と精神の乖離というか矛盾は、ドラマのなかで、回収されないままである。
ダイアログ・イン・ザ・ダークに行って来た。谷崎の『陰影礼賛』がどっか頭の隅にあって、暗闇の色々な「質」を味わいたいという気持ちがあった。
実際行ってみて、暗闇を純粋に味わう暇はあまりなかったように思う。
暗闇は、私にとっては、今までずっと「くらやむ」という動詞的な何かだった。永遠の不動の闇としてあるものではなかった。
ダイアログ・イン・ザ・ダークの会場は、月のない真っ暗闇夜より光の止んだ世界である。これが全盲の世界なのかという驚きはあり、その中で、いかに人との関わりが大事かということはよくわかった。
何かモノがある、誰か人がいる、触れる、聞こえる、香る、そのことが、光をもたらすということもわかる。
だけど、暗闇の本質である「光が止む」ということ、世界が消えた後にただある闇ということの中に、もっともっと、ただ居たかったと思う。
ただある闇を求めて、夜の登山がどうしようもなくしたくなる。天然のニュートラルなダークサイドを歩きたい。友よ。今度は、夜の山に登りましょう。
実際行ってみて、暗闇を純粋に味わう暇はあまりなかったように思う。
暗闇は、私にとっては、今までずっと「くらやむ」という動詞的な何かだった。永遠の不動の闇としてあるものではなかった。
ダイアログ・イン・ザ・ダークの会場は、月のない真っ暗闇夜より光の止んだ世界である。これが全盲の世界なのかという驚きはあり、その中で、いかに人との関わりが大事かということはよくわかった。
何かモノがある、誰か人がいる、触れる、聞こえる、香る、そのことが、光をもたらすということもわかる。
だけど、暗闇の本質である「光が止む」ということ、世界が消えた後にただある闇ということの中に、もっともっと、ただ居たかったと思う。
ただある闇を求めて、夜の登山がどうしようもなくしたくなる。天然のニュートラルなダークサイドを歩きたい。友よ。今度は、夜の山に登りましょう。
今年のクリスマス過ごし方
2008年12月28日 ポエム今年に入ってから、なかなか料理が手につかない日が多かったので、クリスマスとお正月くらいは料理で祝おうと思った。といっても、それまでケーキ以外何も用意していなかったので、ほんとにありあわせの簡単なものばかりだったけど。
朝、と言っても十時頃帰って来た夫とクリスマスブランチ。チキンのホワイトシチューとイチゴと蜂蜜のサンドイッチ、たまごのサンドイッチ、ショウガの紅茶。夫に鉢植えでも買って帰ってと言ったら、ポインセチアみたいなものは思い浮かばなかったらしく、オレンジピンクやピンクの薔薇や黄色いガーベラをかすみ草にくるんだ大きな花束を持ち帰る。三つの花瓶にわけて、小さな部屋はほとんど花の影、お皿にはかすみ草が散っていた。
夫をせき立ててお風呂に入れ、寝室に追いやって、ハリーポッターのペーパーバックを読みっこしながら寝かしつける。五時間ほどそのまま寝かせる。
その間に、お茶を飲みにいったり買い物をして、三時頃から猛然と再び料理。
夫がお客さんからもらってきた、モルドヴァの珍しい赤のスパークリングワインが非常に大きな励みとなり、鳥の足を焼き、クリスマス色の派手な(おしゃれなやつではなく、どちらかといえば子供が喜びそうな感じの)ピラフをつくり、朝のシチューをもとにキノコクリームスープに作り替え、ミモザサラダ風のサラダを作り、気持ちよくお目覚めになった旦那さまの前に、冷やしたモルドヴァをどんと置く。寝ぼけ眼の旦那は、コルク栓が勢い良く天井にぶちあたる衝撃に驚きすぎるくらい驚いて、そこで私は「ほら」って窓の外を指差す。モルドヴァの赤のようなルビー色の美しい夕日が沈む頃、五時ちょっと前から、クリスマスディナーの始まり。
小さくて濃密なブッシュドノエルは、モルドヴァによくあいました。それだけではなく、モルドヴァには何でもあうのです。イチゴでもお肉でもケーキでも。
モルドヴァをあともう少しで飲みきれるというところで、六時半。上野毛の教会の七時半のミサに行かなければ。
あー、忙しい。行ったら行ったで、混み混み、神父のお説教には情熱があって、「苦しい時はみんなアミーゴだ!」という絶叫にも似た呼びかけに笑ったりする人は誰もいない。だって、本当に、ここにいるみんなが、この急激な不景気に喘いでいるのだもの。私たちよりもさらに苦境にいる在日外国人のための募金箱が回って来て、若い男の子たちが奇麗に折った千円や五千円を寄付していました。
そして、私たちはミサから帰ると久しぶりに、十時初の幸福行き列車に乗りました。(脳科学の本に、十時に寝ることは幸福行き列車に乗ることだとありましたので)
今までと大きく変わったことは、プレゼントです。やっぱり年取ったんでしょうか、それとも分別盛りってことでしょうか。今年は、一緒にパートナーリング(私の方のは真ん中に埋め込まれた小さなダイヤが可愛い)を買ったり、ブライドルレザーの財布を贈ったり、ブーツを贈られたりしました。
昔は、もの、特に身の回りのものには非常に無頓着だったのに(ジュエリーとか小物より、CDとか本のほうがよほど価値があった)。でも。長く使えて、しかも何かコンセプトのある「もの」もいいなと思うようになりました。昨今の買い控えに対抗する流れ。
朝、と言っても十時頃帰って来た夫とクリスマスブランチ。チキンのホワイトシチューとイチゴと蜂蜜のサンドイッチ、たまごのサンドイッチ、ショウガの紅茶。夫に鉢植えでも買って帰ってと言ったら、ポインセチアみたいなものは思い浮かばなかったらしく、オレンジピンクやピンクの薔薇や黄色いガーベラをかすみ草にくるんだ大きな花束を持ち帰る。三つの花瓶にわけて、小さな部屋はほとんど花の影、お皿にはかすみ草が散っていた。
夫をせき立ててお風呂に入れ、寝室に追いやって、ハリーポッターのペーパーバックを読みっこしながら寝かしつける。五時間ほどそのまま寝かせる。
その間に、お茶を飲みにいったり買い物をして、三時頃から猛然と再び料理。
夫がお客さんからもらってきた、モルドヴァの珍しい赤のスパークリングワインが非常に大きな励みとなり、鳥の足を焼き、クリスマス色の派手な(おしゃれなやつではなく、どちらかといえば子供が喜びそうな感じの)ピラフをつくり、朝のシチューをもとにキノコクリームスープに作り替え、ミモザサラダ風のサラダを作り、気持ちよくお目覚めになった旦那さまの前に、冷やしたモルドヴァをどんと置く。寝ぼけ眼の旦那は、コルク栓が勢い良く天井にぶちあたる衝撃に驚きすぎるくらい驚いて、そこで私は「ほら」って窓の外を指差す。モルドヴァの赤のようなルビー色の美しい夕日が沈む頃、五時ちょっと前から、クリスマスディナーの始まり。
小さくて濃密なブッシュドノエルは、モルドヴァによくあいました。それだけではなく、モルドヴァには何でもあうのです。イチゴでもお肉でもケーキでも。
モルドヴァをあともう少しで飲みきれるというところで、六時半。上野毛の教会の七時半のミサに行かなければ。
あー、忙しい。行ったら行ったで、混み混み、神父のお説教には情熱があって、「苦しい時はみんなアミーゴだ!」という絶叫にも似た呼びかけに笑ったりする人は誰もいない。だって、本当に、ここにいるみんなが、この急激な不景気に喘いでいるのだもの。私たちよりもさらに苦境にいる在日外国人のための募金箱が回って来て、若い男の子たちが奇麗に折った千円や五千円を寄付していました。
そして、私たちはミサから帰ると久しぶりに、十時初の幸福行き列車に乗りました。(脳科学の本に、十時に寝ることは幸福行き列車に乗ることだとありましたので)
今までと大きく変わったことは、プレゼントです。やっぱり年取ったんでしょうか、それとも分別盛りってことでしょうか。今年は、一緒にパートナーリング(私の方のは真ん中に埋め込まれた小さなダイヤが可愛い)を買ったり、ブライドルレザーの財布を贈ったり、ブーツを贈られたりしました。
昔は、もの、特に身の回りのものには非常に無頓着だったのに(ジュエリーとか小物より、CDとか本のほうがよほど価値があった)。でも。長く使えて、しかも何かコンセプトのある「もの」もいいなと思うようになりました。昨今の買い控えに対抗する流れ。
子供時代は、道草の駅だった場所のことだ。
改札を降りると、長い階段になっている。そこを降りて、そのすすけた町に紛れ込むのが好きだった。だから、駅からのその長い階段を下りるのが嬉しかった。たいていは、学校を(都内にある大学を)さぼることに決めて、家から一番近い駅とほど遠くないその駅で途中下車して、その日一日をファーストフード店で煙草吸いながら本読んでようと思っている。
駅を降りると、駅前を通る車道をはさんで、すすけたようなさえない建物がちまちまと、しかし一枚岩のように迫ってくる。古いビルでできた城塞のような町で、駅前の辺りだけ、妙にごみごみして、迷路みたいになっている。パチンコ屋と魚屋の間の一階がシャッターを閉めたままの小さな建物の二階が、去年マリエンバートで見たかもしれない喫茶店になっている。ある日、ファーストフード店にも飽きた私は、迷路を彷徨ってたまたまその場所を見つけたのだ。それ以来、その駅は、どこをとっても、孤独で自由でプライベートな空間だった。
この土日、かつての道草の駅に二日続けて降りていった。
土曜は旧友と会うため、日曜は父の合唱を聞くためだ。同じ場所の意味合いがかつてとはまったく違ってしまった。
その場所は、今は、親しい友人が勤めていてたまに一緒にランチする場所、家族が年末に集まって食事する場所、親戚や知人がアマチュアコンサートする場所になった。
駅前の城壁の裏にある迷路はそのまま、とおりすぎて、オープンなスペースを行ったり来たりする。かつてのあの淀んだ場所に物理的に踏み込んだとしても、もう大した意味はないのだろうか。行ったり来たりしながら、また、今、この手が考えている。私の今は、昨日と今日よりも、あのよどんだ場所に近い気がする。
改札を降りると、長い階段になっている。そこを降りて、そのすすけた町に紛れ込むのが好きだった。だから、駅からのその長い階段を下りるのが嬉しかった。たいていは、学校を(都内にある大学を)さぼることに決めて、家から一番近い駅とほど遠くないその駅で途中下車して、その日一日をファーストフード店で煙草吸いながら本読んでようと思っている。
駅を降りると、駅前を通る車道をはさんで、すすけたようなさえない建物がちまちまと、しかし一枚岩のように迫ってくる。古いビルでできた城塞のような町で、駅前の辺りだけ、妙にごみごみして、迷路みたいになっている。パチンコ屋と魚屋の間の一階がシャッターを閉めたままの小さな建物の二階が、去年マリエンバートで見たかもしれない喫茶店になっている。ある日、ファーストフード店にも飽きた私は、迷路を彷徨ってたまたまその場所を見つけたのだ。それ以来、その駅は、どこをとっても、孤独で自由でプライベートな空間だった。
この土日、かつての道草の駅に二日続けて降りていった。
土曜は旧友と会うため、日曜は父の合唱を聞くためだ。同じ場所の意味合いがかつてとはまったく違ってしまった。
その場所は、今は、親しい友人が勤めていてたまに一緒にランチする場所、家族が年末に集まって食事する場所、親戚や知人がアマチュアコンサートする場所になった。
駅前の城壁の裏にある迷路はそのまま、とおりすぎて、オープンなスペースを行ったり来たりする。かつてのあの淀んだ場所に物理的に踏み込んだとしても、もう大した意味はないのだろうか。行ったり来たりしながら、また、今、この手が考えている。私の今は、昨日と今日よりも、あのよどんだ場所に近い気がする。