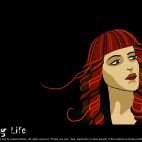またもや夜中にミルクを飲んでいる。
本当は、この本の感想を書くつもりはなかった。
本当は、伊藤整の『街と村 生物祭 イカルス失墜』(講談社文藝文庫, 1993)の感想を書きたいのである。でも、写真がないから、この本の表紙で繋ぎ止めよう。
『樹液そして果実』には、伊藤整についての短い文章がある。
それによると、伊藤整と言えば『小説の方法』だが、「『小説の方法』の最も重要な基盤は、日本文化とギリシア文化との相似といふとらへ方である。両者はいづれもキリスト教の戒律と無縁であつたから、たとへばホメロスのやうに、たとへば徳田秋聲のやうに、エゴをむきだしに提出して、人間性への残酷な認識に到達することができたと伊藤は考へていたらしい」とあり、なるほどと思う。もしかしたら、ギリシア悲劇やプラトン以前のギリシア的思考を想起したニーチェのような、木田元のようなことを考えていたのかもしれないと思い、腑に落ちるところがあった。
丸谷才一は、しかし、伊藤整は評論家としては、西洋十九世紀のリアリズム文学の宣言を真に受けた近代日本文学の伝統にずいぶん忠実であって、小説家としても「ずいぶん無理して」いたのではないかと言っている。
でも、小説家としての伊藤整の真価は、そういうところにあるのだろうかと疑問に思う。
私は、『街と村 生物祭 イカルス失墜』と読んで、伊藤整は、西洋近代の自然科学的自然観みたいなものに照らされない〈暗がり〉を作品の中に保持し得た作家だと思った。 その暗がりは、本当に日本的なものであって、〈近代の光〉に照らし出されたあらゆる小説には決して読み取れないような暗さ、言語に住まう自然なのである。「街と村」の特に「幽鬼の村」では、主人公は、生者であると同時に死者であり、そこにいると同時に不在であり、私小説であるにもかかわらず不思議なことに人間のいない植物だけの時空間が立ち現れ、植物達が語りだしたりする。宗教であれ、学問であれ、文学であれ、イデオロギーであれ、日本人のどうしようもない土着性とその滑稽さは拭いがたいほどの濃密な自然であるという気がした。痛々しいほど克明な内面の描写さえも、関東大震災後の昭和、のっぺりした不安な時代を生きる自己を全身記号と化して書いているようなそんな執念を感じるのだが、その体験は作家の身体という暗がりへの接触であると思う。
自然は、私達の中にあるのか、外にあるのか、私達は、その一部なのか、それとも絶対的な他者なのか、3.11以来ずっと心にある問いである。
余談だけれど、『街と村 生物祭 イカルス失墜』に収録されている中で、一番好きだったのは、「石狩」という短編で、父の死後、歌子という狂女を追い求めて石狩に旅に出た主人公が汽車の中で、胡散臭い宗教家の胡散臭い因縁話を端で聞いているうちに滝のように涙をこぼしてしまい、しまいに「莫迦野郎!」「俺のことは君の説教に関係がないんだ」と、仁王立ちで大声を張り上げ、怒りを爆発させ、車内で注目を浴びてしまう箇所がやたら好きだった。伊藤整、面白い。
本当は、この本の感想を書くつもりはなかった。
本当は、伊藤整の『街と村 生物祭 イカルス失墜』(講談社文藝文庫, 1993)の感想を書きたいのである。でも、写真がないから、この本の表紙で繋ぎ止めよう。
『樹液そして果実』には、伊藤整についての短い文章がある。
それによると、伊藤整と言えば『小説の方法』だが、「『小説の方法』の最も重要な基盤は、日本文化とギリシア文化との相似といふとらへ方である。両者はいづれもキリスト教の戒律と無縁であつたから、たとへばホメロスのやうに、たとへば徳田秋聲のやうに、エゴをむきだしに提出して、人間性への残酷な認識に到達することができたと伊藤は考へていたらしい」とあり、なるほどと思う。もしかしたら、ギリシア悲劇やプラトン以前のギリシア的思考を想起したニーチェのような、木田元のようなことを考えていたのかもしれないと思い、腑に落ちるところがあった。
丸谷才一は、しかし、伊藤整は評論家としては、西洋十九世紀のリアリズム文学の宣言を真に受けた近代日本文学の伝統にずいぶん忠実であって、小説家としても「ずいぶん無理して」いたのではないかと言っている。
でも、小説家としての伊藤整の真価は、そういうところにあるのだろうかと疑問に思う。
私は、『街と村 生物祭 イカルス失墜』と読んで、伊藤整は、西洋近代の自然科学的自然観みたいなものに照らされない〈暗がり〉を作品の中に保持し得た作家だと思った。 その暗がりは、本当に日本的なものであって、〈近代の光〉に照らし出されたあらゆる小説には決して読み取れないような暗さ、言語に住まう自然なのである。「街と村」の特に「幽鬼の村」では、主人公は、生者であると同時に死者であり、そこにいると同時に不在であり、私小説であるにもかかわらず不思議なことに人間のいない植物だけの時空間が立ち現れ、植物達が語りだしたりする。宗教であれ、学問であれ、文学であれ、イデオロギーであれ、日本人のどうしようもない土着性とその滑稽さは拭いがたいほどの濃密な自然であるという気がした。痛々しいほど克明な内面の描写さえも、関東大震災後の昭和、のっぺりした不安な時代を生きる自己を全身記号と化して書いているようなそんな執念を感じるのだが、その体験は作家の身体という暗がりへの接触であると思う。
自然は、私達の中にあるのか、外にあるのか、私達は、その一部なのか、それとも絶対的な他者なのか、3.11以来ずっと心にある問いである。
余談だけれど、『街と村 生物祭 イカルス失墜』に収録されている中で、一番好きだったのは、「石狩」という短編で、父の死後、歌子という狂女を追い求めて石狩に旅に出た主人公が汽車の中で、胡散臭い宗教家の胡散臭い因縁話を端で聞いているうちに滝のように涙をこぼしてしまい、しまいに「莫迦野郎!」「俺のことは君の説教に関係がないんだ」と、仁王立ちで大声を張り上げ、怒りを爆発させ、車内で注目を浴びてしまう箇所がやたら好きだった。伊藤整、面白い。
夜中に起き出して、ミルクを温め、『なずな』を読む。
熱帯夜なのにもかかわらず、夜中に冷たいミルクを飲みたくなかった。
『なずな』読了。
堀江敏幸は、今、一番、読んでいて心地いい。
なんと言っても、眼差しが優しい。
『雪沼とその周辺』と『いつか王子駅で』は、本当に素晴らしかった。
『なずな』は、その二冊ほどの完成度はないかなと思う。
主題は、赤ん坊の成長だから、作品が最後に向かって凝結していくというより、ふわあっと広がっていく感じがする。作品のリズムだって、赤ん坊が眠って泣いてミルク飲んで排泄しておしめを変えるというサイクルが何度も繰り返されることによって、進行していくのだ。
完成度の高さとは関係なく、至福の小説だと思う。
ちょうど、『マイバックページ』とか『ブラックスワン』のような、敗北の物語を見た後だったから、それとは別の次元へと開かれた本が読めて良かった。
とはいえ、『マイバックページ』も『ブラックスワン』も愛おしく感じたし好きではあった。
「とくに昼間、喫茶店モードになっているときの《美津保》の空気は、適度に乾いて爽快になっている。以前は仕込みのにおいや湿気が店内のあちこちに沈んでいたのだが、幸いにもそれはなくなった。ただし、清潔さと店の魅力とはべつもので、じめっとしてその湿り気にいろんなにおいがとけ込んでいるここの雰囲気を、私は嫌いではなかった。むしろ好きだった。」p.133
このいろいろがとけ込んでいる雰囲気が、かのカレーピラフの美味しそうなことにつながっていくような気がする。
本当に久しぶりにここに書いている。
そろそろまた夜中の読書ノートが必要になってきたのかもしれない。
『なずな』の前は、井伏鱒二の『黒い雨』を読んでいた。
いっぱい書き留めておきたいことはあるような気がする。
熱帯夜なのにもかかわらず、夜中に冷たいミルクを飲みたくなかった。
『なずな』読了。
堀江敏幸は、今、一番、読んでいて心地いい。
なんと言っても、眼差しが優しい。
『雪沼とその周辺』と『いつか王子駅で』は、本当に素晴らしかった。
『なずな』は、その二冊ほどの完成度はないかなと思う。
主題は、赤ん坊の成長だから、作品が最後に向かって凝結していくというより、ふわあっと広がっていく感じがする。作品のリズムだって、赤ん坊が眠って泣いてミルク飲んで排泄しておしめを変えるというサイクルが何度も繰り返されることによって、進行していくのだ。
完成度の高さとは関係なく、至福の小説だと思う。
ちょうど、『マイバックページ』とか『ブラックスワン』のような、敗北の物語を見た後だったから、それとは別の次元へと開かれた本が読めて良かった。
とはいえ、『マイバックページ』も『ブラックスワン』も愛おしく感じたし好きではあった。
「とくに昼間、喫茶店モードになっているときの《美津保》の空気は、適度に乾いて爽快になっている。以前は仕込みのにおいや湿気が店内のあちこちに沈んでいたのだが、幸いにもそれはなくなった。ただし、清潔さと店の魅力とはべつもので、じめっとしてその湿り気にいろんなにおいがとけ込んでいるここの雰囲気を、私は嫌いではなかった。むしろ好きだった。」p.133
このいろいろがとけ込んでいる雰囲気が、かのカレーピラフの美味しそうなことにつながっていくような気がする。
本当に久しぶりにここに書いている。
そろそろまた夜中の読書ノートが必要になってきたのかもしれない。
『なずな』の前は、井伏鱒二の『黒い雨』を読んでいた。
いっぱい書き留めておきたいことはあるような気がする。
週刊朝日緊急増刊 朝日ジャーナル [雑誌]
2009年7月12日 読書
五月の末くらいだったか夫がラジオで朝日ジャーナルが復刊してそのことを大竹まことが喋っていてとてもオモシロそうだよと教えてくれた。
一冊まるごと刺激的な、雑誌というには密度の濃い、読み飛ばしできない中味。
内容は、今の日本はどうなのというものだが、単純に面白いのは、浅田彰×宇野常寛×東浩紀の対談の中で繰り広げられる静かな大げんか。特に、東浩紀は、浅田彰に対してなんという口のきき方をするのだろうとハラハラドキドキ。それに、批評が生き残らないと困ると思っているくせに、政治の「流れに抵抗する」ことも放棄、浅田や宇野といった別の世代の批評家が立っている前提も否定、自分のようにリアリティーを持っている者のみが生き残るのだと、あくまで傲慢な感じ。行き詰まっている場所で戯れるしかないのが批評なのだろうか。
それと辻元清美×中森明夫×秋元康の新人類対談。「あの時ぼくらは若かった」という懐古と言い訳と反省と感謝。 秋元康、マーケティングなんかヒットとはなんの関係もないと言い切る。「森の中でみんな出口がわからなくてうろうろして、「こっちが出口らしいよ」っていう流行に乗って、出口の方に行こうとするんですよ。だけど、みんなが行かない方に自信を持って一人が歩き始めると、絶対その後をついていくんだよね。実はそれくらい自信満々じゃないとダメなんです。」こういうこと言うのが、新人類じゃないかなと思う。
見田宗介、柄谷行人、鶴見俊介、斉藤貴男、雨宮処凛、山森亮を読んでいると、やっぱり、鶴見俊介の言う「日露戦争以来の大国主義を見直せ」という考え方が、説得力を持って浮き上がってくる感じがする(それを軸にして、他の人たちのものを読むと、自然とつながってくるのではないか)。日露戦争以来の、というのは、本当は、日清戦争以来の……なんじゃないかと思う。
日本が近代国家として成長した代償は「いのち」だったと、小松裕の『日本の歴史十四 「いのち」と帝国日本』では言われている。
日清戦争以来、「近代国家権力の本質ともいうべき「いのちをめぐる政治」」が出現する。「それをひとことで表現するならば、「いのち」の序列化である。人びとのいのちに序列をつけ、一方は優遇し一方は抹殺するという政策を実施し、それを人びとに当然のこととして受容させていく政策のことである。」
もちろん、今は戦時中じゃないないけど、まるで、戦争が起こる直前のような不穏な空気を感じ取っている人もいるんじゃないだろうか。それはおおもとで「いのち」が保証されない不安感からくるのではないか。「いのち」を支える政治をしてほしいと思う。
一冊まるごと刺激的な、雑誌というには密度の濃い、読み飛ばしできない中味。
内容は、今の日本はどうなのというものだが、単純に面白いのは、浅田彰×宇野常寛×東浩紀の対談の中で繰り広げられる静かな大げんか。特に、東浩紀は、浅田彰に対してなんという口のきき方をするのだろうとハラハラドキドキ。それに、批評が生き残らないと困ると思っているくせに、政治の「流れに抵抗する」ことも放棄、浅田や宇野といった別の世代の批評家が立っている前提も否定、自分のようにリアリティーを持っている者のみが生き残るのだと、あくまで傲慢な感じ。行き詰まっている場所で戯れるしかないのが批評なのだろうか。
それと辻元清美×中森明夫×秋元康の新人類対談。「あの時ぼくらは若かった」という懐古と言い訳と反省と感謝。 秋元康、マーケティングなんかヒットとはなんの関係もないと言い切る。「森の中でみんな出口がわからなくてうろうろして、「こっちが出口らしいよ」っていう流行に乗って、出口の方に行こうとするんですよ。だけど、みんなが行かない方に自信を持って一人が歩き始めると、絶対その後をついていくんだよね。実はそれくらい自信満々じゃないとダメなんです。」こういうこと言うのが、新人類じゃないかなと思う。
見田宗介、柄谷行人、鶴見俊介、斉藤貴男、雨宮処凛、山森亮を読んでいると、やっぱり、鶴見俊介の言う「日露戦争以来の大国主義を見直せ」という考え方が、説得力を持って浮き上がってくる感じがする(それを軸にして、他の人たちのものを読むと、自然とつながってくるのではないか)。日露戦争以来の、というのは、本当は、日清戦争以来の……なんじゃないかと思う。
日本が近代国家として成長した代償は「いのち」だったと、小松裕の『日本の歴史十四 「いのち」と帝国日本』では言われている。
日清戦争以来、「近代国家権力の本質ともいうべき「いのちをめぐる政治」」が出現する。「それをひとことで表現するならば、「いのち」の序列化である。人びとのいのちに序列をつけ、一方は優遇し一方は抹殺するという政策を実施し、それを人びとに当然のこととして受容させていく政策のことである。」
もちろん、今は戦時中じゃないないけど、まるで、戦争が起こる直前のような不穏な空気を感じ取っている人もいるんじゃないだろうか。それはおおもとで「いのち」が保証されない不安感からくるのではないか。「いのち」を支える政治をしてほしいと思う。
徐京植 多和田葉子『ソウルーベルリン 玉突き書簡』
2009年6月18日 読書岩波書店 2008.4
徐京植は1951年京都生まれ、韓国滞在中の在日朝鮮人二世作家。
多和田葉子は1960年東京生まれ、ベルリン在住の作家。
2007.2から2007.11までに交わされた二人の書簡集がこの『ソウルーベルリン 玉突き書簡』だ。
とてもおもしろかった。一信ごとにテーマが生まれ、十のテーマをめぐり、二十回の手紙のやり取り。読者は、多和田葉子の記述の中で、世界の変貌を目の当たりにし、意識がわあっとそれこそ高速で開けていくのを感じるのではないか。一方、徐京植の記述からは、私たちがそこにはまりこんでいまだに逃れられないでいる歴史の癒しがたい傷の深さを思い出すのだと思う。私自身は、多和田葉子にずいぶん救われる思いがした。昔、ここでブログを別のタイトル別の名前でやっていたとき、相互リンクの方に「あなたは、多和田葉子を参考にするといいんじゃないか」と言っていただいたのだが、私はそのときは多和田葉子の良さがわからず、せっかく薦めてくれた彼にとても失礼をしてしまったと思う。今では、本当にその時のこと、その人に感謝している。
本のことに戻ると、十章あるうちのすべての章(信)ごとに、抜き書きしたい文章があり、また関係なく見えるすべてのテーマが、深く結びついている。
一番重いテーマは、やはり日本の自殺率の高さに触れている第九信の「殉教」だろう。
ヨーロッパでは、イスラム原理主義者による自爆テロが起こるたびに、日本の「カミカゼ」特攻隊が引き合いに出され、「不可解な不気味なオリエント」という安易な括られかたをしてしまい、しかも日本には「死を賞賛する文化」があるという認識が定着しているという。
「イスラム教自体はキリスト教と同じで、決して自殺賞賛などしていません。だから、テロリストは日本にヒントを得たという仮説が出るのも無理はないわけです。去年ヨルダンに行った時に、日本の特攻精神を褒めたたえたアラビア語の詩を見せてもらい、ぎょっとしました。なぜ死を賞賛する文化がうまれてしまったのかを世界に向かって説明する責任が今新たにうまれて来ている気がするのです。」p.140
このことは、今の日本の自殺率の高さや、いじめられている子供の「親や先生に話すくらいなら死んだ方がまし」という気持ちや、「死んで尊厳を守る」という考え方、「死んで責任を取る」という態度、「死ぬ覚悟でやっている」というような言い方、武士の切腹、三島の美学、「特攻隊はお国のために自分の意志で死んでいった」かのような言説のすべてにつながっていく話で、よくよく考えてみれば、まったく他人事ではなかった。
私の父は今でも「国のために命を捧げるのは当然だろ」としきりに言いたがることがあるし、母は「老醜をさらすくらいなら早く死んだ方がまし」とすごく若いときから言い続けて、本当に若死にしてしまったという経緯がある。私は、そういう両親の言語から身を守るために自分の意志でキリスト教に入信したり、学問的な論理的な言語体系で心を武装しようとした時もあったくらいなのだ。
ただ、両親の名誉のために言うなら、彼らが、キリスト教の悪口を言いながらも娘を幼児のときからミッション系の学校に通わせ、大人になると学問をはじめてかわいげがなくなっていくことにいやいやながらもどこか安堵して見守っていたのはたぶん事実であって、結局、父や母の死生観は、本音ではなく、どこか演技としての要素があったのではないかと思う。
これは、日本の「死を賞賛する文化」の中の、死を演劇的なものにして人生そのものを舞台にしたいという根深い欲求を、私の父も母もどこかで植え付けられていたけれど、でも本質的なところではそれに抗っていたということなのだと思う。
「自殺とは、誇りを持って、あるいは絶望して、あるいは虚無感に身を任せて、個人が命を断つということではないようです。自殺は生というよりは性の表現形態の一つで、演劇的要素が強く、個人ではなく複数の人間のできごとであるということです。みんなに殺されると言っていいかもしれません。」p.138
これをルネジラールなら、人間の人間化の過程にあった「一体全員の暴力」と呼ぶだろう。それはいまだに繰り返され、文化によっては賞賛されることさえあり、日本の文化にはその傾向があるということかもしれない。
だけど、自殺をいかなる意味でも賞賛しない立場からすれば、それこそは野蛮、動物や野性回帰するのとは逆方向の、人間にしかない野蛮である。そう感じる人は、なんとしてもそれを阻止しなければならないと感じ、自分の出来るやり方で自殺を阻止しようとする。そこには膨大なエネルギ−が投入されることになる。
私は、そんな多くの人々を敗北させる演劇的な死よりも、動物的な死の方が、美しさの点ではるかに勝っていると思う。
徐京植は、金子文子の死を挙げて、それが「国家」から「性愛」を取り戻す死だったとしている。だけど、それは、英雄的な死を特権化して、一般的な自殺をとるにたらないものとするハイデッガー的な考え方に似てしまう。
また、彼は、自殺をなくすためには「生きやすい世の中にすること」と言うが(もちろん制度はどうにかしなければならないが)、そんなことより、もしかしたら、「演劇的な死に方につながる演劇的な生き方をやめる」という方向転換が一番必要なのではないかと思ってしまう。美学の転換である。
否応もなく人間である野蛮を昇華させるために、演劇そのものや諸々の芸術のジャンルがあるのに、なぜ、わざわざ演劇的な生き方や死に方をする必要があるのだろう。
私の母も、そういう生き方をもう少し早くにやめていたらもっと長く生きて、もっと話し合えたろうにと思う。悪口を言う人はいるかもしれないけれど、演劇な生き方をやめるのを本気で止める人はいない、と思う。むしろだれもが、そこから降りたがっているのではないだろうか。美学はその外部が見えなければ恐ろしいものだ。死を賞賛する文化を支えている美学は操作かもしれないのに、それに気づくことさえないのだから残酷である。
徐京植は1951年京都生まれ、韓国滞在中の在日朝鮮人二世作家。
多和田葉子は1960年東京生まれ、ベルリン在住の作家。
2007.2から2007.11までに交わされた二人の書簡集がこの『ソウルーベルリン 玉突き書簡』だ。
とてもおもしろかった。一信ごとにテーマが生まれ、十のテーマをめぐり、二十回の手紙のやり取り。読者は、多和田葉子の記述の中で、世界の変貌を目の当たりにし、意識がわあっとそれこそ高速で開けていくのを感じるのではないか。一方、徐京植の記述からは、私たちがそこにはまりこんでいまだに逃れられないでいる歴史の癒しがたい傷の深さを思い出すのだと思う。私自身は、多和田葉子にずいぶん救われる思いがした。昔、ここでブログを別のタイトル別の名前でやっていたとき、相互リンクの方に「あなたは、多和田葉子を参考にするといいんじゃないか」と言っていただいたのだが、私はそのときは多和田葉子の良さがわからず、せっかく薦めてくれた彼にとても失礼をしてしまったと思う。今では、本当にその時のこと、その人に感謝している。
本のことに戻ると、十章あるうちのすべての章(信)ごとに、抜き書きしたい文章があり、また関係なく見えるすべてのテーマが、深く結びついている。
一番重いテーマは、やはり日本の自殺率の高さに触れている第九信の「殉教」だろう。
ヨーロッパでは、イスラム原理主義者による自爆テロが起こるたびに、日本の「カミカゼ」特攻隊が引き合いに出され、「不可解な不気味なオリエント」という安易な括られかたをしてしまい、しかも日本には「死を賞賛する文化」があるという認識が定着しているという。
「イスラム教自体はキリスト教と同じで、決して自殺賞賛などしていません。だから、テロリストは日本にヒントを得たという仮説が出るのも無理はないわけです。去年ヨルダンに行った時に、日本の特攻精神を褒めたたえたアラビア語の詩を見せてもらい、ぎょっとしました。なぜ死を賞賛する文化がうまれてしまったのかを世界に向かって説明する責任が今新たにうまれて来ている気がするのです。」p.140
このことは、今の日本の自殺率の高さや、いじめられている子供の「親や先生に話すくらいなら死んだ方がまし」という気持ちや、「死んで尊厳を守る」という考え方、「死んで責任を取る」という態度、「死ぬ覚悟でやっている」というような言い方、武士の切腹、三島の美学、「特攻隊はお国のために自分の意志で死んでいった」かのような言説のすべてにつながっていく話で、よくよく考えてみれば、まったく他人事ではなかった。
私の父は今でも「国のために命を捧げるのは当然だろ」としきりに言いたがることがあるし、母は「老醜をさらすくらいなら早く死んだ方がまし」とすごく若いときから言い続けて、本当に若死にしてしまったという経緯がある。私は、そういう両親の言語から身を守るために自分の意志でキリスト教に入信したり、学問的な論理的な言語体系で心を武装しようとした時もあったくらいなのだ。
ただ、両親の名誉のために言うなら、彼らが、キリスト教の悪口を言いながらも娘を幼児のときからミッション系の学校に通わせ、大人になると学問をはじめてかわいげがなくなっていくことにいやいやながらもどこか安堵して見守っていたのはたぶん事実であって、結局、父や母の死生観は、本音ではなく、どこか演技としての要素があったのではないかと思う。
これは、日本の「死を賞賛する文化」の中の、死を演劇的なものにして人生そのものを舞台にしたいという根深い欲求を、私の父も母もどこかで植え付けられていたけれど、でも本質的なところではそれに抗っていたということなのだと思う。
「自殺とは、誇りを持って、あるいは絶望して、あるいは虚無感に身を任せて、個人が命を断つということではないようです。自殺は生というよりは性の表現形態の一つで、演劇的要素が強く、個人ではなく複数の人間のできごとであるということです。みんなに殺されると言っていいかもしれません。」p.138
これをルネジラールなら、人間の人間化の過程にあった「一体全員の暴力」と呼ぶだろう。それはいまだに繰り返され、文化によっては賞賛されることさえあり、日本の文化にはその傾向があるということかもしれない。
だけど、自殺をいかなる意味でも賞賛しない立場からすれば、それこそは野蛮、動物や野性回帰するのとは逆方向の、人間にしかない野蛮である。そう感じる人は、なんとしてもそれを阻止しなければならないと感じ、自分の出来るやり方で自殺を阻止しようとする。そこには膨大なエネルギ−が投入されることになる。
私は、そんな多くの人々を敗北させる演劇的な死よりも、動物的な死の方が、美しさの点ではるかに勝っていると思う。
徐京植は、金子文子の死を挙げて、それが「国家」から「性愛」を取り戻す死だったとしている。だけど、それは、英雄的な死を特権化して、一般的な自殺をとるにたらないものとするハイデッガー的な考え方に似てしまう。
また、彼は、自殺をなくすためには「生きやすい世の中にすること」と言うが(もちろん制度はどうにかしなければならないが)、そんなことより、もしかしたら、「演劇的な死に方につながる演劇的な生き方をやめる」という方向転換が一番必要なのではないかと思ってしまう。美学の転換である。
否応もなく人間である野蛮を昇華させるために、演劇そのものや諸々の芸術のジャンルがあるのに、なぜ、わざわざ演劇的な生き方や死に方をする必要があるのだろう。
私の母も、そういう生き方をもう少し早くにやめていたらもっと長く生きて、もっと話し合えたろうにと思う。悪口を言う人はいるかもしれないけれど、演劇な生き方をやめるのを本気で止める人はいない、と思う。むしろだれもが、そこから降りたがっているのではないだろうか。美学はその外部が見えなければ恐ろしいものだ。死を賞賛する文化を支えている美学は操作かもしれないのに、それに気づくことさえないのだから残酷である。
迷宮レストラン—クレオパトラから樋口一葉まで
2009年6月7日 読書
レシピを実現する前に返却日が来てしまった図書館の本。
シェイクスピア、コロンブス、バッハ、ドラキュラ伯爵などのために用意された料理を作って食べてみたかった。
今日はターミネータ4の先行上映を夫と観に行った。結果は、クリスチャン・ベールの力をもってしても、この程度か……という印象。
脚本が、もう一つという気がする。
先月末には女友達と『ゴエモン』に行ったが、そっちはかなり満足した。大沢たかおよかった。
同じアメリカ資本でも、日本人に作らせたものの方が出来が良くなっている気がする。
こういうエンタテイメントを見るとなんか夏だな、と思う。
シェイクスピア、コロンブス、バッハ、ドラキュラ伯爵などのために用意された料理を作って食べてみたかった。
今日はターミネータ4の先行上映を夫と観に行った。結果は、クリスチャン・ベールの力をもってしても、この程度か……という印象。
脚本が、もう一つという気がする。
先月末には女友達と『ゴエモン』に行ったが、そっちはかなり満足した。大沢たかおよかった。
同じアメリカ資本でも、日本人に作らせたものの方が出来が良くなっている気がする。
こういうエンタテイメントを見るとなんか夏だな、と思う。
ドラマ『ハゲタカ』の冒頭は、「世の中には金のある不幸と金のない不幸、二つの不幸しかない」とかなんとかだったと思う。でもドラマの終盤で田中みん演じる技術者が言うように、お金には本当の実体がないとしたら、お金にまつわる不幸とは、結局なんだということになる。
『森に眠る魚』に描かれる不幸は、すべて、「比較」から来る不幸と言える。
自分と他人を比較する以前に、自分を受け入れて現状をつかんでいるなら(それが地に足をつけた生き方というものだけど)、生き方はとてもシンプルになるはずである。たとえば、成就しようとしまいと、自分の目的を定めて綿密に計画を立て手帖に書く。そしたら、それをいったん忘れて今を生きる。享受する。他人には無理に親切にする必要はない。ただ、自分に対しても人に対しても暴力を振るわないようにする。物理的にはあたりまえだが、とりわけ言葉で暴力をふるわないようにする。それだけで平和で幸せで美しい人間になれそうな気がする。他人と比較さえしなければ、まったくシンプルに幸せでいられる。子供がいるとそうもいかないというのは欺瞞である。子供は、いつも親の欲望と親たちが作り上げた愚かな一般性の犠牲になるから、怨恨に満ちた世界がいつまでも終わらないのだ。
格差だなんだと言っても、本当は、この日本で貧困などありえない。村中をあさっても村人全員が食べ物を見つけられないとか、そういう世界レベルの貧困には遠く及ばない。それでも、他者との比較によって、苛烈な貧困意識が生まれ続ける。それを回避するためだったら、ほとんどなんでもやりかねない状況である。
「比較する」人には、どんな言葉も届かない。連帯しようとしても、慰めようとしても、楽しませようとしても、バカにするか悪者にされるのがオチである。なぜなら比較する人は、いつも自分か他人をバカにするか悪者にするかしているので、バカにも悪者にもしない、自分のせいにも他人のせいにもしない、という本当に単純なことが出来ない。でも実は、これさえ出来れば、不足という脅迫観念はほぼなくなる。愛の不足さえも、底が割れる。愛じゃなくてただ一方的に愛されたい人を誰が愛すだろうか、無償の愛という伝統を学ぶ気もないくせにという底である。あるがままの現実は、誰にとっても切実に厳しいのである。他人の不平不満につきあうほどのゆとりはない。それほど、人は、今の自分をそれぞれ愛しんでいるのである。それがわかれば、誰も無理なんかしなくなる。今あることを大事にして、自分にとって必要なことを見極めようとし、自分の身に起こる危険なサインにも敏感になる。経済感覚もしっかりしてきて、お金とも仲良くなる。
いいこと尽くめなのに、やっぱり比較する人は比較しないではいられない。その外で生きたことがないからである。外に出ることは真空状態に身をさらすことだと感じている。なぜなら、比較の世界ではかくも具体的なものがあふれ、センスだとか個性だとかの才能らしきものを発揮できるのに、外の世界には、具体的なものが何もない。外に出たら、本当は、何に価値があるのかわからない。そこで生きたことがないから当然なのだ。結局、比較の世界の外で生きるためには、あらゆる具象と親由来の一般的価値基準を手放さなくてはならないという恐怖に怯え始め、今度は外の世界を死後の天国であるかのように夢見始めるのだ。
この小説の描く苦しみは、比較の世界の外部がない、出口なし、自由なしの苦しみである。ほとんど地獄である。それでも角田光代は、心優しいと思う。
比較の世界の外は、真空じゃないよ、ちゃんと具体的なこと・ものがあるよ、と教えている。
でも、なんだか読んでいてとても悲しい気持ちになったのは、登場人物たちが、残酷なほど不公平な描かれかたをしていたこと。容姿、所得、家族、すべてに恵まれている人は、心にもゆとりがあり、爽やかな生き方をしている。一方でその反対の人は、物語上でも奪われる一方であり、奪われても仕方がないような言動を繰り返すのである。
本当に本の外から声をかけたくなる。休息が必要だ。肌や髪や歯が美しくなり、安物でもゆっくり本当に好きな服を時間をかけて選び、自分で自分の身体をよくマッサージして、自分で作った上等な食べ物と睡眠を取り、たくさんの褒め言葉を与え、そうやってあなたも恵まれた人になっていくんだと祈ってしまう。
実際はそんなふうに声をかけられない。無理して、自分も大変だと力説し、あえて自分を貶めて語り、それで、自分も相手も嫌いになってしまったりする。相手のことを理解しようとするうちにその言葉を内面化し、いつのまにかぼろぼろになっていたりする。きっと、相手には想像もつかないことだろう。
『森に眠る魚』に描かれる不幸は、すべて、「比較」から来る不幸と言える。
自分と他人を比較する以前に、自分を受け入れて現状をつかんでいるなら(それが地に足をつけた生き方というものだけど)、生き方はとてもシンプルになるはずである。たとえば、成就しようとしまいと、自分の目的を定めて綿密に計画を立て手帖に書く。そしたら、それをいったん忘れて今を生きる。享受する。他人には無理に親切にする必要はない。ただ、自分に対しても人に対しても暴力を振るわないようにする。物理的にはあたりまえだが、とりわけ言葉で暴力をふるわないようにする。それだけで平和で幸せで美しい人間になれそうな気がする。他人と比較さえしなければ、まったくシンプルに幸せでいられる。子供がいるとそうもいかないというのは欺瞞である。子供は、いつも親の欲望と親たちが作り上げた愚かな一般性の犠牲になるから、怨恨に満ちた世界がいつまでも終わらないのだ。
格差だなんだと言っても、本当は、この日本で貧困などありえない。村中をあさっても村人全員が食べ物を見つけられないとか、そういう世界レベルの貧困には遠く及ばない。それでも、他者との比較によって、苛烈な貧困意識が生まれ続ける。それを回避するためだったら、ほとんどなんでもやりかねない状況である。
「比較する」人には、どんな言葉も届かない。連帯しようとしても、慰めようとしても、楽しませようとしても、バカにするか悪者にされるのがオチである。なぜなら比較する人は、いつも自分か他人をバカにするか悪者にするかしているので、バカにも悪者にもしない、自分のせいにも他人のせいにもしない、という本当に単純なことが出来ない。でも実は、これさえ出来れば、不足という脅迫観念はほぼなくなる。愛の不足さえも、底が割れる。愛じゃなくてただ一方的に愛されたい人を誰が愛すだろうか、無償の愛という伝統を学ぶ気もないくせにという底である。あるがままの現実は、誰にとっても切実に厳しいのである。他人の不平不満につきあうほどのゆとりはない。それほど、人は、今の自分をそれぞれ愛しんでいるのである。それがわかれば、誰も無理なんかしなくなる。今あることを大事にして、自分にとって必要なことを見極めようとし、自分の身に起こる危険なサインにも敏感になる。経済感覚もしっかりしてきて、お金とも仲良くなる。
いいこと尽くめなのに、やっぱり比較する人は比較しないではいられない。その外で生きたことがないからである。外に出ることは真空状態に身をさらすことだと感じている。なぜなら、比較の世界ではかくも具体的なものがあふれ、センスだとか個性だとかの才能らしきものを発揮できるのに、外の世界には、具体的なものが何もない。外に出たら、本当は、何に価値があるのかわからない。そこで生きたことがないから当然なのだ。結局、比較の世界の外で生きるためには、あらゆる具象と親由来の一般的価値基準を手放さなくてはならないという恐怖に怯え始め、今度は外の世界を死後の天国であるかのように夢見始めるのだ。
この小説の描く苦しみは、比較の世界の外部がない、出口なし、自由なしの苦しみである。ほとんど地獄である。それでも角田光代は、心優しいと思う。
比較の世界の外は、真空じゃないよ、ちゃんと具体的なこと・ものがあるよ、と教えている。
でも、なんだか読んでいてとても悲しい気持ちになったのは、登場人物たちが、残酷なほど不公平な描かれかたをしていたこと。容姿、所得、家族、すべてに恵まれている人は、心にもゆとりがあり、爽やかな生き方をしている。一方でその反対の人は、物語上でも奪われる一方であり、奪われても仕方がないような言動を繰り返すのである。
本当に本の外から声をかけたくなる。休息が必要だ。肌や髪や歯が美しくなり、安物でもゆっくり本当に好きな服を時間をかけて選び、自分で自分の身体をよくマッサージして、自分で作った上等な食べ物と睡眠を取り、たくさんの褒め言葉を与え、そうやってあなたも恵まれた人になっていくんだと祈ってしまう。
実際はそんなふうに声をかけられない。無理して、自分も大変だと力説し、あえて自分を貶めて語り、それで、自分も相手も嫌いになってしまったりする。相手のことを理解しようとするうちにその言葉を内面化し、いつのまにかぼろぼろになっていたりする。きっと、相手には想像もつかないことだろう。
『グランド・フィナーレ』 と足利えん罪事件
2009年6月6日 読書
この小説が、今話題の足利事件のえん罪を、(暗に)訴っえている本だという講義を受けたことがある。
すなわち、ロリコン、倒錯、あるいは無垢な子供しか愛せないという性癖、もしくは単なる子供好きが、足利事件においては不当にも断罪され、えん罪の被害者を生んでしまった、と阿部和重は、この小説を通して言っているそうだ。(実際には足利事件のえん罪の犠牲者は、ロリコンですらなかったようなので、いったい何がなんだかわからないけれども。)
普通に読んでるだけなら、決して浮かび上がってこない編み込まれた意図-糸だ。
でも、もし本当にそうなら、見事だと思う。さすが第一線の作家の仕事だと思う(なかなか売れないようだけれど)。この作品の作者、阿部和重は、おそらく強度のロリコンである。たぶん、彼にとって、「ロリコン」は間違いなく「愛」の範疇に入るのだ。自分にとってはそうであることを語った上で、倒錯者は殺人者ではない、と小説の中で明言しているのである。
保坂和志が『小説の自由』の中で言っていたことを思い出す。ある人にとって「愛」ではなことを、別のある人は「愛」だと信じているときがある。それゆえに、言葉を媒体とする小説は難しい。しかし、一般的でない「愛」や「善」について語り、それによって一般的である「ふり」をやめるしか、自己に集中し、真実を語ることは出来ないのかもしれない。そういうことをやろうとする小説はやっぱりなんかえらいと思う。
すなわち、ロリコン、倒錯、あるいは無垢な子供しか愛せないという性癖、もしくは単なる子供好きが、足利事件においては不当にも断罪され、えん罪の被害者を生んでしまった、と阿部和重は、この小説を通して言っているそうだ。(実際には足利事件のえん罪の犠牲者は、ロリコンですらなかったようなので、いったい何がなんだかわからないけれども。)
普通に読んでるだけなら、決して浮かび上がってこない編み込まれた意図-糸だ。
でも、もし本当にそうなら、見事だと思う。さすが第一線の作家の仕事だと思う(なかなか売れないようだけれど)。この作品の作者、阿部和重は、おそらく強度のロリコンである。たぶん、彼にとって、「ロリコン」は間違いなく「愛」の範疇に入るのだ。自分にとってはそうであることを語った上で、倒錯者は殺人者ではない、と小説の中で明言しているのである。
保坂和志が『小説の自由』の中で言っていたことを思い出す。ある人にとって「愛」ではなことを、別のある人は「愛」だと信じているときがある。それゆえに、言葉を媒体とする小説は難しい。しかし、一般的でない「愛」や「善」について語り、それによって一般的である「ふり」をやめるしか、自己に集中し、真実を語ることは出来ないのかもしれない。そういうことをやろうとする小説はやっぱりなんかえらいと思う。
源氏物語 巻一 (講談社文庫)
2009年5月9日 読書
五島美術館に行ったら、たまたまなのだが、源氏物語絵巻の展示をやっていた。
揉箔を散らし様々な透かし模様の入った紙に、美しい外国語のようなやまとことばが、流れるように細い細い字でしたためらているのだった。
絵より字の方に洗練を、字の震えや息遣いに精神を感じてしまった。
昨日の大きな虹、今日の赤い大きな月、八十歳を越える歌人の大家さん(学生時代&同棲時代の)から連絡あり、近く尋ねることになり、なんだか神秘的な大きな流れを感じたりする。
揉箔を散らし様々な透かし模様の入った紙に、美しい外国語のようなやまとことばが、流れるように細い細い字でしたためらているのだった。
絵より字の方に洗練を、字の震えや息遣いに精神を感じてしまった。
昨日の大きな虹、今日の赤い大きな月、八十歳を越える歌人の大家さん(学生時代&同棲時代の)から連絡あり、近く尋ねることになり、なんだか神秘的な大きな流れを感じたりする。
「その緑色の大きな目はとても美しく、虹彩の周囲には細かい金箔が散りばめられていた。そのとき僕は、目には年齢がない、死ぬときも子供の目のまま、ある日世界に見開かれ、その世界を手放すことなく死ぬんだと思ったことを覚えている。」p.41
「そうなれば、ただでさえ世界の縁にいるわれわれはなおさら縁へと追いやられる。そのことがしばしば恐ろしい事態を招く。一部の人にとって孤立することは、奇妙な反芻へ、ねじれた危うい思考の足場へと導くことがあるからだ。まさにそのせいで、冬の幾晩かのうちに奇妙な建築家の本性をあらわにした人を、僕はたくさん知っている。」p.49
「すでに言ったように、彼は口数が少なかった。ひどく無口だった。彼を見ているうちに、聖人の顔を思い浮かべることもあった。聖徳とはとてもおもしろいものだ。たまたまそういうものと出会うと、人はよくほかのもの、まったく別のものと取り違えてしまう。たとえば無関心、からかい、陰謀、冷酷、傲慢、それに軽蔑とか。誤解したあげく、腹を立てる。最悪の行動に出てしまう。聖人たちがいつも殉教してしまうのは、おそらくそのためなのだ。」p.43
「そうなれば、ただでさえ世界の縁にいるわれわれはなおさら縁へと追いやられる。そのことがしばしば恐ろしい事態を招く。一部の人にとって孤立することは、奇妙な反芻へ、ねじれた危うい思考の足場へと導くことがあるからだ。まさにそのせいで、冬の幾晩かのうちに奇妙な建築家の本性をあらわにした人を、僕はたくさん知っている。」p.49
「すでに言ったように、彼は口数が少なかった。ひどく無口だった。彼を見ているうちに、聖人の顔を思い浮かべることもあった。聖徳とはとてもおもしろいものだ。たまたまそういうものと出会うと、人はよくほかのもの、まったく別のものと取り違えてしまう。たとえば無関心、からかい、陰謀、冷酷、傲慢、それに軽蔑とか。誤解したあげく、腹を立てる。最悪の行動に出てしまう。聖人たちがいつも殉教してしまうのは、おそらくそのためなのだ。」p.43
『告白』といっても、殺意の告白である。殺したい相手への殺意の告白だ。そういう行為を、本当に、「告白」という日本語で言い表していいのだろうか。アウグスティヌスは、「自分に最も近いことはなにか」と自問自答しながら大著『告白』を書いたものだが、殺意の告白は「脅迫」って言わないか? それとも、殺意こそは、我々の「最も近いこと」になったのだろうか。
しかし、あまり、深刻なことを言わない方がいいだろう。これは、正真正銘のエンターテイメントなのだから。めくるめく「殺意」たちの繰り広げるショウである。読者は、あっというまに、「殺意」の暴露を楽しみ始める。
最初は、言葉が汚いなと漠然と感じる。『風花』の川上弘美の文章と比べると雲泥の差がある。
『風花』は、とにかく文章が素晴らしかった。読後一ヶ月目にしてようやく内容を自分がどう読んだか客観視できるが、読んだ当初は川上弘美の文章力にぼう然自失していた。一文一文の伝わりかたが半端じゃなかった。無駄な言葉がなく論理の飛躍もない文章、一分の隙もない。
「みっともないことなんだな、他人と共にやってゆこうと努力することって。
のゆりの鼻から、涙が出てくる。目からはほとんど出ず、鼻だけから、すうすうと流れ出てくる。ほんとうに、みっともないよね、わたし。つぶやきながら、のゆりは卓哉にぎゅっとかじりつく。卓哉の腕が少しだけあがって、のゆりの背中に、力なく、まわされる。」『風花』p.173
中盤の山場のシーンである。今読んでもどうしてこういう文章になるのか、はっきり思い出せる。一文一文が必然性を持っているからである。
『告白』は、逆に、論理の飛躍だらけ、言葉には「毒」を滲ませるための余計なノイズがいっぱいある。だから、文章が、荒れて汚く感じるのである。しかしそれらはすべて、意図されたものなのだ。
「馬鹿ですか? ラブレターの中には、散々、馬鹿という言葉が使われていました。あなたはいったい自分を何様だと思っているのでしょう。あなたがいったい何を生み出し、あなたが馬鹿と見下す人たちに、何の恩恵を与えているというのですか?」『告白』p.257
一番最後の章の最初の方の文章である。気持ちはわかるけど、特に必要な文とは思われない。特に「馬鹿ですか?」は、相手に「バカ!」と言っているのか、「バカって言いましたか?」と聞いているのかわからない。しかし、最後の章なので、論理より効果、ノイズを駆使して、渾身の一撃を加えなければならないのだろう。
ここにでてくる「告白者」数名は、ほぼ全員殺意の持ち主であり、殺人の実行犯である。殺意は、バトンリレーのように、告白者から告白者へと手渡されていく。殺意はミッションである。それゆえ、章のタイトルは、ミッションに生きる告白者を称して、「聖職者」「殉教者」「慈愛者」「信奉者」「伝道者」となっている。物語は、見事な円を描いて、最初の語り部のもとに戻ってくる。最後に、決定的な制裁が下される。完璧である。
でも私は、最後に、もう一章、「死者」の章がほしかったと思う。なぜなら、最後の文の論理の飛躍が許せなかったからである。
「ねえ、渡辺君。これが本当の復讐であり、あなたの更生の第一歩だとは思いませんか?」『告白』p.268
ネタばれになるが、これは、自分の子供を殺された女教師が、犯人の男子生徒の母親を殺すことによって、「復讐」を果たし、それが「更生」の第一歩だと言っている文だ。なぜ母親を殺すのかと言うと、こういう下りがある。
「あなたの気持ちは母親だけにしか向いていないのに、被害を被るのはいつも、母親以外の人物です。
あなたの世界に、あなたと愛するママしか存在しないのなら、ママを殺しなさい。」
きっとここで、大いに腑に落ちる人もいるだろうし、まったく腑に落ちない人もいるだろう。
これは、作家から読者への問いかけでもあるのだろう。私の願望にすぎないが、作家の本当の視座は、主人公「子供を殺された女教師」ではなく、この作品の中で唯一、殺意の告白者ではない本当の告白者「母を弟に殺された姉」「被害者と加害者両方の家族」にある、と感じる。一瞬しか出てこないが、その身を縮めて書いているさまが、本当の「はじまり」という気がした。
だとしたら、なおさら、「はじまり」に対する「終わり」がないような気がする。収まりを付けたいので、私が勝手に書いておきます。
「死者
私は読者という死者です。あなたの告白によって何度も殺されました。そうです。牛乳に混入された毒で殺されたのでもなく、大学にしかけられた爆薬で殺されたのでもありません。読むという行為によって殺されたのです。
事実、告白者の一人か二人、もしかしたら全員が、手を下すことによってではなく、言葉によって人を殺したのです。悪意のある言葉、相手になんとか打撃を与えようとする言葉によって殺されたのです。
でも、安心して下さい。本当の死者は、こんな風に語ったりしませんから。
無惨に死んだ私のために、死んでくれだの、復讐してくれだの、言いません。
死者は黙して語らず、これが原則です。死者は戻ってこないし、語ったりもしません。だから、死者のために復讐するのは、死者のためでなく、生者のためです。
生者が、自分の中のまだ死んでいない死者たちの言葉を聞いて、さぞ悔しかろう、さぞ無念だったろうと心を痛めてくれるのです。
しかし、残念ながら、死者の死はそんなものではありません。容赦のないものです。私には、死が生者の問題を解決するとは思えません。死は、生きるものにとっては、謎そのものではないでしょうか。なぜ、生者は、謎の方向へ、解決を求めるのでしょうか。自分たちのわかる限りの方向へ、解決を押し進めないのでしょうか。なぜ、死が、「更生の第一歩」なのでしょうか。
他者に、ただ痛みを与えたい。なぜなら、痛みを覚えたから。告白者たちが言っていることはそういうことです。彼らにとって、おのれの不幸こそは正義なのです。正義を通すためには、相手に不幸を与える必要があるのです。死者には関係がありません。痛みとともに死んだのですから。」
しかし、あまり、深刻なことを言わない方がいいだろう。これは、正真正銘のエンターテイメントなのだから。めくるめく「殺意」たちの繰り広げるショウである。読者は、あっというまに、「殺意」の暴露を楽しみ始める。
最初は、言葉が汚いなと漠然と感じる。『風花』の川上弘美の文章と比べると雲泥の差がある。
『風花』は、とにかく文章が素晴らしかった。読後一ヶ月目にしてようやく内容を自分がどう読んだか客観視できるが、読んだ当初は川上弘美の文章力にぼう然自失していた。一文一文の伝わりかたが半端じゃなかった。無駄な言葉がなく論理の飛躍もない文章、一分の隙もない。
「みっともないことなんだな、他人と共にやってゆこうと努力することって。
のゆりの鼻から、涙が出てくる。目からはほとんど出ず、鼻だけから、すうすうと流れ出てくる。ほんとうに、みっともないよね、わたし。つぶやきながら、のゆりは卓哉にぎゅっとかじりつく。卓哉の腕が少しだけあがって、のゆりの背中に、力なく、まわされる。」『風花』p.173
中盤の山場のシーンである。今読んでもどうしてこういう文章になるのか、はっきり思い出せる。一文一文が必然性を持っているからである。
『告白』は、逆に、論理の飛躍だらけ、言葉には「毒」を滲ませるための余計なノイズがいっぱいある。だから、文章が、荒れて汚く感じるのである。しかしそれらはすべて、意図されたものなのだ。
「馬鹿ですか? ラブレターの中には、散々、馬鹿という言葉が使われていました。あなたはいったい自分を何様だと思っているのでしょう。あなたがいったい何を生み出し、あなたが馬鹿と見下す人たちに、何の恩恵を与えているというのですか?」『告白』p.257
一番最後の章の最初の方の文章である。気持ちはわかるけど、特に必要な文とは思われない。特に「馬鹿ですか?」は、相手に「バカ!」と言っているのか、「バカって言いましたか?」と聞いているのかわからない。しかし、最後の章なので、論理より効果、ノイズを駆使して、渾身の一撃を加えなければならないのだろう。
ここにでてくる「告白者」数名は、ほぼ全員殺意の持ち主であり、殺人の実行犯である。殺意は、バトンリレーのように、告白者から告白者へと手渡されていく。殺意はミッションである。それゆえ、章のタイトルは、ミッションに生きる告白者を称して、「聖職者」「殉教者」「慈愛者」「信奉者」「伝道者」となっている。物語は、見事な円を描いて、最初の語り部のもとに戻ってくる。最後に、決定的な制裁が下される。完璧である。
でも私は、最後に、もう一章、「死者」の章がほしかったと思う。なぜなら、最後の文の論理の飛躍が許せなかったからである。
「ねえ、渡辺君。これが本当の復讐であり、あなたの更生の第一歩だとは思いませんか?」『告白』p.268
ネタばれになるが、これは、自分の子供を殺された女教師が、犯人の男子生徒の母親を殺すことによって、「復讐」を果たし、それが「更生」の第一歩だと言っている文だ。なぜ母親を殺すのかと言うと、こういう下りがある。
「あなたの気持ちは母親だけにしか向いていないのに、被害を被るのはいつも、母親以外の人物です。
あなたの世界に、あなたと愛するママしか存在しないのなら、ママを殺しなさい。」
きっとここで、大いに腑に落ちる人もいるだろうし、まったく腑に落ちない人もいるだろう。
これは、作家から読者への問いかけでもあるのだろう。私の願望にすぎないが、作家の本当の視座は、主人公「子供を殺された女教師」ではなく、この作品の中で唯一、殺意の告白者ではない本当の告白者「母を弟に殺された姉」「被害者と加害者両方の家族」にある、と感じる。一瞬しか出てこないが、その身を縮めて書いているさまが、本当の「はじまり」という気がした。
だとしたら、なおさら、「はじまり」に対する「終わり」がないような気がする。収まりを付けたいので、私が勝手に書いておきます。
「死者
私は読者という死者です。あなたの告白によって何度も殺されました。そうです。牛乳に混入された毒で殺されたのでもなく、大学にしかけられた爆薬で殺されたのでもありません。読むという行為によって殺されたのです。
事実、告白者の一人か二人、もしかしたら全員が、手を下すことによってではなく、言葉によって人を殺したのです。悪意のある言葉、相手になんとか打撃を与えようとする言葉によって殺されたのです。
でも、安心して下さい。本当の死者は、こんな風に語ったりしませんから。
無惨に死んだ私のために、死んでくれだの、復讐してくれだの、言いません。
死者は黙して語らず、これが原則です。死者は戻ってこないし、語ったりもしません。だから、死者のために復讐するのは、死者のためでなく、生者のためです。
生者が、自分の中のまだ死んでいない死者たちの言葉を聞いて、さぞ悔しかろう、さぞ無念だったろうと心を痛めてくれるのです。
しかし、残念ながら、死者の死はそんなものではありません。容赦のないものです。私には、死が生者の問題を解決するとは思えません。死は、生きるものにとっては、謎そのものではないでしょうか。なぜ、生者は、謎の方向へ、解決を求めるのでしょうか。自分たちのわかる限りの方向へ、解決を押し進めないのでしょうか。なぜ、死が、「更生の第一歩」なのでしょうか。
他者に、ただ痛みを与えたい。なぜなら、痛みを覚えたから。告白者たちが言っていることはそういうことです。彼らにとって、おのれの不幸こそは正義なのです。正義を通すためには、相手に不幸を与える必要があるのです。死者には関係がありません。痛みとともに死んだのですから。」
最近の夫婦を扱った小説は、地味に面白い。特に最近の傾向なのかもしれないが、自己批判的「妻」批判がすごい、と私は思う。そのすごさは、とても地味でわかりにくいけれども、「妻」という存在の仕方のドン詰まり感を余すところなく書いているところに現れている。
川上弘美の『風花』にしろ井上荒野の『切羽へ』にしろ、主人公の「妻」は弱者だ。いわゆる「女、子供」という言い方に典型的に現れるような弱者であり、そういう「私、感傷的で、弱いんです、天然の生き物なんです、守って下さい」という女性像を女性作家がわざわざ書いて見せているところに、女性による地味な非-フェミニズム(古いフェミニズムにとってかわるもう一つのフェミニズムかもしれないが)みたいなものを感じる。
例えば、『風花』が夫に裏切られた妻による自立の物語だったらあんまり面白くない。結婚という制度はそもそもどこか変だ、というありきたりな違和感しか残さない。しかし、逆に、夫婦の純愛物語として読めるかというと、読めなくはないけれどそう言ったら台無しという気がする。少なくとも、これは「雨降って地固まる」んではなく(主人公の親の世代の話ならそういう話になったと暗示させるエピソードがある)、雨降ったら地が溶けてしまうのが、昨今の「妻」物語なのだ。
雨が降ったら「妻」というあり方はすぐにも溶けてなくなるのだが、『風花』の主人公は、なかなか自立を選択しない。かといって、元の鞘にももどらない。「元の鞘」なんてものはもともとなかったのかもしれないなどと考えあぐねながら、ずっとぐちゃぐちゃした地面を歩き続けるのである。
そういう脈絡で読むと、『風花』のラストは、地味だが強烈で、納得させるものがあった。「地味だけど強烈」と言うと、相反するものの特徴が共存しているという印象だが、この小説が描く「妻 のゆり」は、ほんとに地味にして強烈な感じがする。まず、非常にいらいらさせられる。しかし、いらいらするのは、こっちのせいであって、「のゆり」のせいではない。「のゆり」の「のゆりらしさ」にいらいらするのは、多分私の方に原因があるのだろう。だって、「のゆり」の個性は本当に野に咲く天然の百合のようにただ咲いているわけなんだから。そして、そういう「のゆりらしさ」を守って来たのは、ひとえに「夫 卓哉」との結婚に他ならないことは容易に察しがつく。
そういう意味で、この小説の「夫 卓哉」像は、なかなか奥が深い。夫 卓哉は、結婚生活を「どこにもない美しい山に登る」イメージで始めた人物で、そのせいか不思議な仮面をかぶっている。その仮面を脱がせようという奮闘努力が、「のゆり」の愛の物語になっていくわけである。しかしこの愛の物語が、ハッピーエンドかと言うと、一言では言いあらわせないようになっていて、流石である。
けっこう切ない、「やりきれない」ラストだったと思う。それは、やっぱり、作家自身の、どこか身を痛めるような「結婚」批判の成果だからだと思う。
川上弘美の『風花』にしろ井上荒野の『切羽へ』にしろ、主人公の「妻」は弱者だ。いわゆる「女、子供」という言い方に典型的に現れるような弱者であり、そういう「私、感傷的で、弱いんです、天然の生き物なんです、守って下さい」という女性像を女性作家がわざわざ書いて見せているところに、女性による地味な非-フェミニズム(古いフェミニズムにとってかわるもう一つのフェミニズムかもしれないが)みたいなものを感じる。
例えば、『風花』が夫に裏切られた妻による自立の物語だったらあんまり面白くない。結婚という制度はそもそもどこか変だ、というありきたりな違和感しか残さない。しかし、逆に、夫婦の純愛物語として読めるかというと、読めなくはないけれどそう言ったら台無しという気がする。少なくとも、これは「雨降って地固まる」んではなく(主人公の親の世代の話ならそういう話になったと暗示させるエピソードがある)、雨降ったら地が溶けてしまうのが、昨今の「妻」物語なのだ。
雨が降ったら「妻」というあり方はすぐにも溶けてなくなるのだが、『風花』の主人公は、なかなか自立を選択しない。かといって、元の鞘にももどらない。「元の鞘」なんてものはもともとなかったのかもしれないなどと考えあぐねながら、ずっとぐちゃぐちゃした地面を歩き続けるのである。
そういう脈絡で読むと、『風花』のラストは、地味だが強烈で、納得させるものがあった。「地味だけど強烈」と言うと、相反するものの特徴が共存しているという印象だが、この小説が描く「妻 のゆり」は、ほんとに地味にして強烈な感じがする。まず、非常にいらいらさせられる。しかし、いらいらするのは、こっちのせいであって、「のゆり」のせいではない。「のゆり」の「のゆりらしさ」にいらいらするのは、多分私の方に原因があるのだろう。だって、「のゆり」の個性は本当に野に咲く天然の百合のようにただ咲いているわけなんだから。そして、そういう「のゆりらしさ」を守って来たのは、ひとえに「夫 卓哉」との結婚に他ならないことは容易に察しがつく。
そういう意味で、この小説の「夫 卓哉」像は、なかなか奥が深い。夫 卓哉は、結婚生活を「どこにもない美しい山に登る」イメージで始めた人物で、そのせいか不思議な仮面をかぶっている。その仮面を脱がせようという奮闘努力が、「のゆり」の愛の物語になっていくわけである。しかしこの愛の物語が、ハッピーエンドかと言うと、一言では言いあらわせないようになっていて、流石である。
けっこう切ない、「やりきれない」ラストだったと思う。それは、やっぱり、作家自身の、どこか身を痛めるような「結婚」批判の成果だからだと思う。
野村佐紀子写真集 夜間飛行
2009年2月8日 読書
去年、新聞の書評でこの写真集のことを知った。
「暗くもうろうとした画面のなか、煙突群が煙を吐き出し、一糸まとわぬ男がこちらを見つめる。斬新な男性ヌード写真で知られる著者が七年間撮りためた風景と人物写真の集大成だ。シャワーのようなテールランプ、ベッドでくつろぐ男のたばこの日。超小型カメラでとらえた光は濃い闇を引き立たせる脇役にすぎない。ざらついた紙の手触りが粒の粗い画面と相まって、見る者の感覚を強く刺激する。」日経12月
これを読んですぐ、ああ、私の見たいものだ、と思った。
すぐ、地元の図書館にリクエストして、さっさと大きいところからお取り寄せしてくれるだろうと思っていたら、やけに時間がかかる。確かめたら、その地元の小さな図書館が発注して買ってくれていたのだ。きっといろいろ装備に時間がかかったのだろう、やっと、昨日、借りて来れた。
ざらざらする手触りの頁を繰りながら、そうだ、おなじだ、嬉しい、と思う。
私も、野村佐紀子さんと同じように(同じようなんて僭越だろうか)、ずっと前から、だいたい思春期の始まり頃から、暗がりそのものに恋している。見ながら、ああ、そうそう、こういう薄闇だ、と思う。
外がすみれ色に染まった車中の暗がり、ベッドの柔らかいくぼみに眠る闇、いつのまにか道に同化している闇に似た意識、お互いの影でつながってしまう身体。夜に近づくと、風景と身体はどうしてこう似てくるのだろうと思ってしまう。
ほんとに若い頃は、父や母や家族の前では、こうしたことが絶対語りえないことだった。私がどこでもなく誰でもない薄暗がりに大恋愛しているなんて。
この作家好き。キムギドクの『悪い男』の諸々の(岬や港や彼の身体の)シルエットと同じくらい好き。
以下覚え書き:
「野村佐紀子 1967年 山口県下関市生まれ。91年より写真家・荒木経惟氏に師事。主に男性の裸体を中心とした湿度のある独特の作品世界を追求し続ける。93年より国内はもとよりヨーロッパ、アジアなどでも精力的個展・グループ展を開催衣する。著書に『裸ノ時間』(平凡社)、『愛ノ時間』(BPM)、『闇の音』(山口県立美術館)、『黒猫』(t.i.g)、『tukuyomi』『近藤良平』(MATCH&Co.)などがある。」
「暗くもうろうとした画面のなか、煙突群が煙を吐き出し、一糸まとわぬ男がこちらを見つめる。斬新な男性ヌード写真で知られる著者が七年間撮りためた風景と人物写真の集大成だ。シャワーのようなテールランプ、ベッドでくつろぐ男のたばこの日。超小型カメラでとらえた光は濃い闇を引き立たせる脇役にすぎない。ざらついた紙の手触りが粒の粗い画面と相まって、見る者の感覚を強く刺激する。」日経12月
これを読んですぐ、ああ、私の見たいものだ、と思った。
すぐ、地元の図書館にリクエストして、さっさと大きいところからお取り寄せしてくれるだろうと思っていたら、やけに時間がかかる。確かめたら、その地元の小さな図書館が発注して買ってくれていたのだ。きっといろいろ装備に時間がかかったのだろう、やっと、昨日、借りて来れた。
ざらざらする手触りの頁を繰りながら、そうだ、おなじだ、嬉しい、と思う。
私も、野村佐紀子さんと同じように(同じようなんて僭越だろうか)、ずっと前から、だいたい思春期の始まり頃から、暗がりそのものに恋している。見ながら、ああ、そうそう、こういう薄闇だ、と思う。
外がすみれ色に染まった車中の暗がり、ベッドの柔らかいくぼみに眠る闇、いつのまにか道に同化している闇に似た意識、お互いの影でつながってしまう身体。夜に近づくと、風景と身体はどうしてこう似てくるのだろうと思ってしまう。
ほんとに若い頃は、父や母や家族の前では、こうしたことが絶対語りえないことだった。私がどこでもなく誰でもない薄暗がりに大恋愛しているなんて。
この作家好き。キムギドクの『悪い男』の諸々の(岬や港や彼の身体の)シルエットと同じくらい好き。
以下覚え書き:
「野村佐紀子 1967年 山口県下関市生まれ。91年より写真家・荒木経惟氏に師事。主に男性の裸体を中心とした湿度のある独特の作品世界を追求し続ける。93年より国内はもとよりヨーロッパ、アジアなどでも精力的個展・グループ展を開催衣する。著書に『裸ノ時間』(平凡社)、『愛ノ時間』(BPM)、『闇の音』(山口県立美術館)、『黒猫』(t.i.g)、『tukuyomi』『近藤良平』(MATCH&Co.)などがある。」
1 2