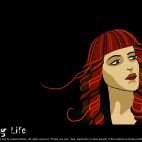チェリーコーク bottle1 (1)
2009年1月14日 読書
松は取れてしまったけれど、2009年おめでとう。
昨年末から持ち越した体調の不安定が、ここにきて落ち着いて来たようだ。
毎年、クリスマス位から松が取れるくらいまでの間、頭が勝手に大回顧展を開いたり、展望台に登ってくれたりするのだが、それもさすがに収まった。
元旦の朝に渋谷の教会にお参りというか礼拝に行き、その帰りにこの本を買った。
中を見て、たちまち脳がはしゃぎ出すの感じ、「脳にいいことだけをやりなさい」という本を斜め読みした後だけに買うまでに至ったのだった。
今改めて見返すと、本にぎっしりお重のように詰め込まれた、おおたうにのイラストは、渋谷の大きな教会の色とりどりの色ガラスに囲まれた空間の感触に似ているな、と思う。すごく楽しいおしゃれの本です。
昨年末から持ち越した体調の不安定が、ここにきて落ち着いて来たようだ。
毎年、クリスマス位から松が取れるくらいまでの間、頭が勝手に大回顧展を開いたり、展望台に登ってくれたりするのだが、それもさすがに収まった。
元旦の朝に渋谷の教会にお参りというか礼拝に行き、その帰りにこの本を買った。
中を見て、たちまち脳がはしゃぎ出すの感じ、「脳にいいことだけをやりなさい」という本を斜め読みした後だけに買うまでに至ったのだった。
今改めて見返すと、本にぎっしりお重のように詰め込まれた、おおたうにのイラストは、渋谷の大きな教会の色とりどりの色ガラスに囲まれた空間の感触に似ているな、と思う。すごく楽しいおしゃれの本です。
今年一番印象に残っている本と言えばこれだ。
マルグリット・デュラスの戦争ノート。
四冊の手書きの草稿ノートをまとめた本なのだが、それぞれのノートがモノとしても作品としても完成度が高く、読み応え見応えがする。
これを読むと、例えば『愛人』が具体的で多様な「貧しさ」について書く過程の中で生まれた作品だとわかる。
彼女の少女時代の有名な出で立ち、男物の帽子、すり切れたワンピース、ヒール、媚態、幼ささえも、彼女たち家族があらゆる意味でとても貧しかったということを意味しているのだとわかる。
夫に死なれた母親の事業がことごとく失敗し、兄たちは粗暴で、隣人たちは侮蔑的
で、「私」はついに卑しく醜い現地の男の白人の女への欲望に身を委ねるのだが、記述は起伏に富んでいて、ユーモアがあり、愛がある。
例えば、「私」は、暴力を振るう兄やそれを容認している母のことを憎みながらも、その異常性について自分以外の誰かが責めるのを許さないし、その実深く愛している。読む側が、彼女と同じように彼らを愛してしまうほど彼らのことを愛しているのだった。もちろん文字は痕跡でしかない。しかし言葉は、鳴り続ける和音とか震動のようなもので、この本はまだずっと聞こえていて欲しい音なのだ。
マルグリット・デュラスの戦争ノート。
四冊の手書きの草稿ノートをまとめた本なのだが、それぞれのノートがモノとしても作品としても完成度が高く、読み応え見応えがする。
これを読むと、例えば『愛人』が具体的で多様な「貧しさ」について書く過程の中で生まれた作品だとわかる。
彼女の少女時代の有名な出で立ち、男物の帽子、すり切れたワンピース、ヒール、媚態、幼ささえも、彼女たち家族があらゆる意味でとても貧しかったということを意味しているのだとわかる。
夫に死なれた母親の事業がことごとく失敗し、兄たちは粗暴で、隣人たちは侮蔑的
で、「私」はついに卑しく醜い現地の男の白人の女への欲望に身を委ねるのだが、記述は起伏に富んでいて、ユーモアがあり、愛がある。
例えば、「私」は、暴力を振るう兄やそれを容認している母のことを憎みながらも、その異常性について自分以外の誰かが責めるのを許さないし、その実深く愛している。読む側が、彼女と同じように彼らを愛してしまうほど彼らのことを愛しているのだった。もちろん文字は痕跡でしかない。しかし言葉は、鳴り続ける和音とか震動のようなもので、この本はまだずっと聞こえていて欲しい音なのだ。
文学における世代的なものと世代を超えた普遍的なもの。
あるいは、民族的なものと民族を超えた普遍的なもの。
その対比が、古井由吉と松浦寿輝の対話の中で、何度も浮き彫りになったような気がする。
その度に、普遍の側に立っている(ように見える)古井由吉の言葉に、大きな安堵を覚える。
日本人とは元来こういう民族で、もはやこういう時代においてはこういう文学しか残されていない……などということは、松浦寿輝も言ってはいなかったと思うけれど、古井由吉の言っていることの中に揺るぎない自由を感じる。
それと、今でも一部の人々の特権であるかのようなアカデミズムを振りかざす身振りを感じる時、文学は多くの読者を失わざる得ないと思った。
あるいは、民族的なものと民族を超えた普遍的なもの。
その対比が、古井由吉と松浦寿輝の対話の中で、何度も浮き彫りになったような気がする。
その度に、普遍の側に立っている(ように見える)古井由吉の言葉に、大きな安堵を覚える。
日本人とは元来こういう民族で、もはやこういう時代においてはこういう文学しか残されていない……などということは、松浦寿輝も言ってはいなかったと思うけれど、古井由吉の言っていることの中に揺るぎない自由を感じる。
それと、今でも一部の人々の特権であるかのようなアカデミズムを振りかざす身振りを感じる時、文学は多くの読者を失わざる得ないと思った。
黄昏の百合の骨 (講談社文庫)
2008年11月23日 読書
(あらすじ) むせ返るほどの百合の花で覆われた洋館に、一人の女子高生理瀬がやってくる。祖母の不審な死を調べるために、留学先のイギリスから、幼少期に育った家に戻って来た。しかしその家には、すでに先客がいる。いつのまにか棲みついた理瀬の二人の義理の叔母、梨南子と梨耶子だ。この二人が洋館に棲みついてからというもの、禍々しいことばかり起こる。まず、理瀬の祖母の死がそうだった。しかも、なぜか洋館の周りでは犬や猫などの死骸でいっぱいだ。どうも誰かが毒を動物に飲ませているらしい。魔女よ出て行け、といった「いやらしい」謎の脅迫状が投函される。近所の美少年が館付近で行方不明になる。そして、ついには、最も疎まれた梨耶子が首に鉄片を刺された姿で変死する。庭に埋められた「何か」を探して、スコップとともに倒れている。
語りの中で、主人公理瀬もまた、決して、無垢なありきたりな少女ではないことが明かされる。彼女は人類の闇の歴史を担う一族の一人だ。
(ここまで来ると華々しいエンターテイメント作品だとわかるが、はるかかなたに『ルパン三世 カリオストロの城』まで見えてくる。)
理瀬の一族の壮大な歴史的な秘密……かつて死体処理場だった地下室……が明るみに出ると同時に、理瀬に殺意を抱き、男友達を亡き者にしようとした犯人もまた判明する。が、その犯人はむしろ意外なほど平凡な少女だった。
平凡であることのルサンチマンをたぎらせた一少女、富と権力と圧倒的な個性に憧れずにはいられない読者の化身であり、「平凡さのなかの狂気と悪意」こそが一番醜い、と作者は言いたげだ。
犯人の身の上のあくまで凡庸な顛末と平行して、洋館の歴史は終わる。その終わりとともに新しい戦いの始まりの合図だろうか、物語を通じて、読者の信頼を勝ち得たはずのもう一人の叔母梨南子が、突如理瀬に襲いかかる。
エンターテイメント。純文学にどっぷり浸かる前はこういうのが好きだった。今でも恩田陸の世界は好き。秋、寒く暗くなる季節に読みたくなる。暖かくちょっと苦いココアと一緒に。でも立て続けにむさぼる心境にはなれなくなってしまった。
語りの中で、主人公理瀬もまた、決して、無垢なありきたりな少女ではないことが明かされる。彼女は人類の闇の歴史を担う一族の一人だ。
(ここまで来ると華々しいエンターテイメント作品だとわかるが、はるかかなたに『ルパン三世 カリオストロの城』まで見えてくる。)
理瀬の一族の壮大な歴史的な秘密……かつて死体処理場だった地下室……が明るみに出ると同時に、理瀬に殺意を抱き、男友達を亡き者にしようとした犯人もまた判明する。が、その犯人はむしろ意外なほど平凡な少女だった。
平凡であることのルサンチマンをたぎらせた一少女、富と権力と圧倒的な個性に憧れずにはいられない読者の化身であり、「平凡さのなかの狂気と悪意」こそが一番醜い、と作者は言いたげだ。
犯人の身の上のあくまで凡庸な顛末と平行して、洋館の歴史は終わる。その終わりとともに新しい戦いの始まりの合図だろうか、物語を通じて、読者の信頼を勝ち得たはずのもう一人の叔母梨南子が、突如理瀬に襲いかかる。
エンターテイメント。純文学にどっぷり浸かる前はこういうのが好きだった。今でも恩田陸の世界は好き。秋、寒く暗くなる季節に読みたくなる。暖かくちょっと苦いココアと一緒に。でも立て続けにむさぼる心境にはなれなくなってしまった。
がぶ飲みするお酒は嫌い。
でも毎夜、食事時や食後に一杯くらいは飲みたい。
夜風が気持ちいい時は、緑の間にキャンドルを灯して、飲み食いする。
そしたらそれだけで毎晩ちっちゃなパーティー気分だ。
いつお客があってもいいようにリビングとリビングの窓のむこうを奇麗にしておこう。
お酒もきのきいたものを常備しておきたい。
とはいえ、ビールは、もうわかっているものばかり。既製品。
ワインも手が出るものはお馴染みばかりになってきた。
だけど日本酒の古酒ってちょっと神秘的だ。
神がかっている。
容れ物が宝石みたいに美しいものがある。
ワインみたいな飲み方ができるものもあって興味深い。
これからの楽しみ。
でも毎夜、食事時や食後に一杯くらいは飲みたい。
夜風が気持ちいい時は、緑の間にキャンドルを灯して、飲み食いする。
そしたらそれだけで毎晩ちっちゃなパーティー気分だ。
いつお客があってもいいようにリビングとリビングの窓のむこうを奇麗にしておこう。
お酒もきのきいたものを常備しておきたい。
とはいえ、ビールは、もうわかっているものばかり。既製品。
ワインも手が出るものはお馴染みばかりになってきた。
だけど日本酒の古酒ってちょっと神秘的だ。
神がかっている。
容れ物が宝石みたいに美しいものがある。
ワインみたいな飲み方ができるものもあって興味深い。
これからの楽しみ。
アイアンマン—トライアスロンにかけた17歳の青春 (ポプラ・リアル・シリーズ)
2008年10月4日 読書
これほど読書しながら、筋肉の動きを意識した小説はなく、また自分自身のナイーヴな「怒り」を過去からの呼び声として聞いた物語も久しい。
自分という大人がこの小説の主人公とほとんど同じ怒りを抱えていること、さらに自分より一歩先をこの主人公がひた走っていることに気づいて愕然とする。
子供ってすごい。大人は勝てない。子供に全力でついて行くしかないのかもしれないと思った。
自分という大人がこの小説の主人公とほとんど同じ怒りを抱えていること、さらに自分より一歩先をこの主人公がひた走っていることに気づいて愕然とする。
子供ってすごい。大人は勝てない。子供に全力でついて行くしかないのかもしれないと思った。
鉛色の甘い夫婦関係。お互いにお互いを匿うような狂おしいどこか閉塞した夫婦関係がよく描かれている。テーマは「妻」、その存在。地味なテーマだ。だから良いのかもしれない。女ではなく妻だ。妻の存在の限界は切り羽で、そこで妻であることのしるしをもらってくる物語。
1 2