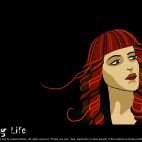ミュージック・アンド・ミー
2009年7月10日 音楽
We’ve been together
For a such a long time
Now music, music and me
Don’t care whether
All our songs rhyme
Now music, music and me
Only know wherever I go
We’re as close as two friends can be
There have been others
But never two lovers
Like music, music and me
Grab a song and come along
You can sing your melody
In your mind you will find
A world of sweet harmony
Birds of a feather
We’ll fly together
Now music, music and me
Music and me
MICHAEL JACKSON, ’MUSIC & ME’, 1973
マイケル・ジャクソンが亡くなったというニュースが駆け巡った直後、半年会っていなかった幼なじみに「マイケルジャクソンが死んでしまったね。ずっと前のことだけど、あなた、好きだったよね」とメールしたら、「よく覚えていたね。そうです、生まれたままのマイケルが好きでした」とかえってきた。もちろん私も(そして多分)彼女も「生まれたままのマイケル」なんて知るはずもなく、知っているのは、「皮膚の色が変わる少し前のマイケル」のイメージでしかない。だけど、彼女らしい優しい口調を伴った「生まれたままのマイケル」という言葉に心惹かれて、漠然とその思い出にひたって過ごしていたら、BSでマイケルジャクソンが亡くなる一週間程前に放送されたというある番組の再放送がやっていて、そこでこの「ミュージック&ミー」が流れた。
それが、まるで本当の遺言のように聞こえたのと、自分の中にある「生まれたままのマイケル」という観念が受肉したように感じたのとで、動揺し、涙さえ出てくるので、自分でも驚いた。それで早速買ってみた。遅ればせながら、私が買った最初のマイケルジャクソンである。ライナーによれば、声変わりする直前にレコーディングされた貴重な一枚でありながら、ヒット曲が生まれなかったために、見過ごされてきたアルバムだという。
確かに、聞いていると、声変わり前の緊張をかかえた孤独な少年の姿が浮かぶ。それでも、最後の二曲’MORNING GLOW’と’MUSIC & ME’には、技巧も年齢も超えた歌の力がみなぎっている。’MUSIC & ME’は、自覚があったのか、変声期を目前にして、静かに子ども時代に別れを告げる少年マイケルの歌心がこちらの胸にも迫ってくるようである。それに対して、’MORNING GLOW’は、早くも変声期の向こう側を見いだしたような、大人のアーチストの力強さがある。この二曲は、何かとても素敵なコントラストだと思う。
これを聞いて思うのは、子ども時代の終わりとは、それがいいものであれわるいものであれ、当の子どもにとって「死」に近いものではないかということである。大人になることは、変声期のような明白な変化を受け入れざるを得ないということであるし、「死」に近いような緊張と苦悩を一人で背負うことにちがいない。十四歳のマイケル・ジャクソンは、この変化を真剣に一歩一歩階段を登るようにして受け止めているように感じられる。そして、ライナーによれば、その数ヶ月後に変声期を終えたマイケルが再び、Dancing Machineという大ヒット曲を聴かせることになるのである。ここに「生まれたままのマイケル」からキングオブポップへの変節を見ようと思えば見れそうな気がする。でも、もう一方には、そんな見方は、いかにも大人らしい単純な見方だという気もするのである。
もしかしたら、14歳の子どもにとって、大人になるということは、一生、変声期を背負うということではないだろうか。大人になるということは、一生、死ぬまで声変わりの緊張と苦悩と闘うことなのではないだろうか。大人の論理を無視すれば、大人時代は「死」の時代であり、その正しい終え方、乗りこえ方を誰も知らないのではないか。このような懐疑は、子ども時代の終わりをまともに背負った人に程、確信にいたるまで、強まってくるものではないか。
もしそうだとしたら、大人への変化は受け入れた(る)けど、内的には、あえて子どもとして生きようという選択をする人がいたとしても、不思議ではない。大人でありながら、子どもとして生きることの方が、徹底した、ごまかしのない生き方だと思うことも出来るはずである。
「ユング的に考えると、ある人がシュシュギュイであるということは、生まれながらにして自己完結型であるか、あるいは、まだ男女が明確に分かれていない幼児性を残していることになるが、それはまた心的なイメージである人間の最終的な理想像、男女両性を兼ね備えた完全な個人の姿にも近いことになる。これに反して、愛情乞食は、自分の欲求に無意識で、やたら相手にしがみつこうとする人たちであるが、情緒的にはより自然で、人間としてはおとなであるということもいえよう。
また、シュシュギュイは、どちらかと言うと自己愛的で自閉的であり、愛情乞食は社会性はあるが、集合的で自立していないと考えてもよい。」秋山さと子,『聖なる男女』青土社,p.36
中島義道が、『人生を半分降りる 哲学的生き方のすすめ』という本の中で、上の一節を挙げ(つまり上の引用は孫引き)、ユングの二つの人間類型について説明している。簡単に言えば、〈シュジュギュイ=子ども、芸術家〉、〈愛情乞食=大人、社会人〉ということらしい。中島は、本の中で、愛情乞食ではなくシュジュギュイとして生きることをすすめている(もっと正確に言うと、社会生活を完全放棄するわけにもいかないので、出来るだけ、なるべく半分、シュジュギュイとして生きようというゆるいすすめ)。
私自身は、シュジュギュイと愛情乞食の二種類の人間がいるというより、二種類の意識があると思う。どちらも理解できるけれども、どちらかでしか生きられないとは思わない。
中島の本を読むと、半分でも全部でも、シュジュギュイとして生きることが、すべての問題の解決と思えてくるのだがそうではない。この本の最後で、シュジュギュイとして生きることの意義みたいなものが哲学的に開陳されるに違いないと期待していたら、最後の頁は、マイケルジャクソンの死のようにまったくもって不可解だった。
シュシュギュイは生き方の選択であって、シュジュギュイとしてどう生きるのか、そこからが長い答えなのだろう。私には、それも大人時代とは何なのかという問いの片方の答えであるような気がする。
For a such a long time
Now music, music and me
Don’t care whether
All our songs rhyme
Now music, music and me
Only know wherever I go
We’re as close as two friends can be
There have been others
But never two lovers
Like music, music and me
Grab a song and come along
You can sing your melody
In your mind you will find
A world of sweet harmony
Birds of a feather
We’ll fly together
Now music, music and me
Music and me
MICHAEL JACKSON, ’MUSIC & ME’, 1973
マイケル・ジャクソンが亡くなったというニュースが駆け巡った直後、半年会っていなかった幼なじみに「マイケルジャクソンが死んでしまったね。ずっと前のことだけど、あなた、好きだったよね」とメールしたら、「よく覚えていたね。そうです、生まれたままのマイケルが好きでした」とかえってきた。もちろん私も(そして多分)彼女も「生まれたままのマイケル」なんて知るはずもなく、知っているのは、「皮膚の色が変わる少し前のマイケル」のイメージでしかない。だけど、彼女らしい優しい口調を伴った「生まれたままのマイケル」という言葉に心惹かれて、漠然とその思い出にひたって過ごしていたら、BSでマイケルジャクソンが亡くなる一週間程前に放送されたというある番組の再放送がやっていて、そこでこの「ミュージック&ミー」が流れた。
それが、まるで本当の遺言のように聞こえたのと、自分の中にある「生まれたままのマイケル」という観念が受肉したように感じたのとで、動揺し、涙さえ出てくるので、自分でも驚いた。それで早速買ってみた。遅ればせながら、私が買った最初のマイケルジャクソンである。ライナーによれば、声変わりする直前にレコーディングされた貴重な一枚でありながら、ヒット曲が生まれなかったために、見過ごされてきたアルバムだという。
確かに、聞いていると、声変わり前の緊張をかかえた孤独な少年の姿が浮かぶ。それでも、最後の二曲’MORNING GLOW’と’MUSIC & ME’には、技巧も年齢も超えた歌の力がみなぎっている。’MUSIC & ME’は、自覚があったのか、変声期を目前にして、静かに子ども時代に別れを告げる少年マイケルの歌心がこちらの胸にも迫ってくるようである。それに対して、’MORNING GLOW’は、早くも変声期の向こう側を見いだしたような、大人のアーチストの力強さがある。この二曲は、何かとても素敵なコントラストだと思う。
これを聞いて思うのは、子ども時代の終わりとは、それがいいものであれわるいものであれ、当の子どもにとって「死」に近いものではないかということである。大人になることは、変声期のような明白な変化を受け入れざるを得ないということであるし、「死」に近いような緊張と苦悩を一人で背負うことにちがいない。十四歳のマイケル・ジャクソンは、この変化を真剣に一歩一歩階段を登るようにして受け止めているように感じられる。そして、ライナーによれば、その数ヶ月後に変声期を終えたマイケルが再び、Dancing Machineという大ヒット曲を聴かせることになるのである。ここに「生まれたままのマイケル」からキングオブポップへの変節を見ようと思えば見れそうな気がする。でも、もう一方には、そんな見方は、いかにも大人らしい単純な見方だという気もするのである。
もしかしたら、14歳の子どもにとって、大人になるということは、一生、変声期を背負うということではないだろうか。大人になるということは、一生、死ぬまで声変わりの緊張と苦悩と闘うことなのではないだろうか。大人の論理を無視すれば、大人時代は「死」の時代であり、その正しい終え方、乗りこえ方を誰も知らないのではないか。このような懐疑は、子ども時代の終わりをまともに背負った人に程、確信にいたるまで、強まってくるものではないか。
もしそうだとしたら、大人への変化は受け入れた(る)けど、内的には、あえて子どもとして生きようという選択をする人がいたとしても、不思議ではない。大人でありながら、子どもとして生きることの方が、徹底した、ごまかしのない生き方だと思うことも出来るはずである。
「ユング的に考えると、ある人がシュシュギュイであるということは、生まれながらにして自己完結型であるか、あるいは、まだ男女が明確に分かれていない幼児性を残していることになるが、それはまた心的なイメージである人間の最終的な理想像、男女両性を兼ね備えた完全な個人の姿にも近いことになる。これに反して、愛情乞食は、自分の欲求に無意識で、やたら相手にしがみつこうとする人たちであるが、情緒的にはより自然で、人間としてはおとなであるということもいえよう。
また、シュシュギュイは、どちらかと言うと自己愛的で自閉的であり、愛情乞食は社会性はあるが、集合的で自立していないと考えてもよい。」秋山さと子,『聖なる男女』青土社,p.36
中島義道が、『人生を半分降りる 哲学的生き方のすすめ』という本の中で、上の一節を挙げ(つまり上の引用は孫引き)、ユングの二つの人間類型について説明している。簡単に言えば、〈シュジュギュイ=子ども、芸術家〉、〈愛情乞食=大人、社会人〉ということらしい。中島は、本の中で、愛情乞食ではなくシュジュギュイとして生きることをすすめている(もっと正確に言うと、社会生活を完全放棄するわけにもいかないので、出来るだけ、なるべく半分、シュジュギュイとして生きようというゆるいすすめ)。
私自身は、シュジュギュイと愛情乞食の二種類の人間がいるというより、二種類の意識があると思う。どちらも理解できるけれども、どちらかでしか生きられないとは思わない。
中島の本を読むと、半分でも全部でも、シュジュギュイとして生きることが、すべての問題の解決と思えてくるのだがそうではない。この本の最後で、シュジュギュイとして生きることの意義みたいなものが哲学的に開陳されるに違いないと期待していたら、最後の頁は、マイケルジャクソンの死のようにまったくもって不可解だった。
シュシュギュイは生き方の選択であって、シュジュギュイとしてどう生きるのか、そこからが長い答えなのだろう。私には、それも大人時代とは何なのかという問いの片方の答えであるような気がする。
(元)職場友とライヴに行ってくる。私はビギナー、彼女は筋金入りのファンである。CDでは聞いていたけどライヴははじめてということで、その感動はやっぱり大きかった。音楽に関しては、「今」を生きていないと批判されても仕方ないほど古いものが好きで、特に邦楽にはあまりに無関心な時代が続いていたので、吉井和哉の日本の音楽史上の位置づけとかは全然わからないけれど、これほどダイレクトにセックスについて歌い、その深みとか暗さとか耐えられない軽さとかめくるめく美と卑猥を語れている人は少ないだろうと思う。セックスは秘匿されるべき否定性だ、それと同時に命を生む創造の最たるものだというアポリアが凄いい勢いでどうしようもなく音楽の中でグルーブし始めるのを感じる。
それと同時に、創作に要しただろう緩やかな時の流れみたいなものを体験できるのが、ライヴというものだったなと思いだした。もともと一年の締めくくりみたいな意味合いのつよい催しらしいし。
自分の身体に蓄積されている時間の流れ、といっても、最近仕事を辞めたなどの大事件ではなく、漠然と町歩きをするようになって知った距離感とか、何の目的もなくスタジオに入って交わしている音のやり取りとか、自分だけに与えられている使命とか、あとは緒形拳が生前に言っていた「巧さを追求して、最後は下手に行き着く。なぜなら、最後は思い一つで動くから」という言葉とか、ミシェル・セールがバレエのことを「場所を譲る芸術」と言っていて、結局人と人の関係はみな身体的なものであり、芸術が美しいのもそこのところなんだなと思ったことなどがその場で再び身体化されるのだった。
もちろん、筋金入り友の方は、もっと細かく吉井和哉そのものを見ていて、今回は前回より、なにか相当「険しい」ものが表情にも選曲にもサービスにも現れていた、と言う。新しいアルバムを完成させたばかりじゃないかと言ったら、去年もそうだったそうだ。それじゃあその険しさとは何か? いつのまにか自分たちの話にすりかえつつ、寒さにも関わらず九段下近辺を十二時近くまで楽しくうろついた。
それと同時に、創作に要しただろう緩やかな時の流れみたいなものを体験できるのが、ライヴというものだったなと思いだした。もともと一年の締めくくりみたいな意味合いのつよい催しらしいし。
自分の身体に蓄積されている時間の流れ、といっても、最近仕事を辞めたなどの大事件ではなく、漠然と町歩きをするようになって知った距離感とか、何の目的もなくスタジオに入って交わしている音のやり取りとか、自分だけに与えられている使命とか、あとは緒形拳が生前に言っていた「巧さを追求して、最後は下手に行き着く。なぜなら、最後は思い一つで動くから」という言葉とか、ミシェル・セールがバレエのことを「場所を譲る芸術」と言っていて、結局人と人の関係はみな身体的なものであり、芸術が美しいのもそこのところなんだなと思ったことなどがその場で再び身体化されるのだった。
もちろん、筋金入り友の方は、もっと細かく吉井和哉そのものを見ていて、今回は前回より、なにか相当「険しい」ものが表情にも選曲にもサービスにも現れていた、と言う。新しいアルバムを完成させたばかりじゃないかと言ったら、去年もそうだったそうだ。それじゃあその険しさとは何か? いつのまにか自分たちの話にすりかえつつ、寒さにも関わらず九段下近辺を十二時近くまで楽しくうろついた。
Hummingbird in Forest of Space(DVD付初回限定盤)
2008年12月21日 音楽
年末、吉井和哉のライヴに行くことに決まる。職場の友が好きで、聞き始めたのだが、このアルバム……宇宙という深い森に羽ばたきその中心の蜜を吸うハミングバードと言うコンセプトのアルバムがとても気に入ってしまった。そして、入手困難なチケットがとれたという朗報。今年の年末はこれか。去年の暮れは、『千年鶴』、韓国のパンソリが年を締めくくる音楽だった。今年は、「ワセドン3」だ。預言者の歌だ。
ザ・ローリング・ストーンズ×マーティン・スコセッシ「シャイン・ア・ライト」O.S.T.
2008年12月11日 音楽
何年か前のことだけど、身の回りに、音楽(バンド、とりわけロック)をやっている人たちが多くいて、精一杯かっこつけてる彼らのことをやっかんで、ある女友達が吐き捨てるように言ったのを思い出す。「いくら音楽やったって、現実には、日本じゃサザンオールスターズくらいしか食えてないんだよっ」
これはもしかたら眩しい友人たちへのやっかみであるばかりじゃなく、事実に近い現実をも言い表していたのかもしれない。私だって、嘘かまことか、「清志郎ですら食えてないらしい」とか凄い大御所が実は「金に汚い」とかよく聞かされたものだ。
近頃だって、贅沢の限りを尽くした小室哲哉が、いつの間にかまったく売れなくなって、詐欺でつかまってびっくりした。
音楽の世界における勝者が、どういう人たちのことなのかわからない。
しかし、ローリングストーンズを勝者と言わずして、誰を勝者と呼ぼうか。
ただし、曲の権利をすべて、ミックとキースが持っていることを考えれば、ストーンズというバンドの中にも、歴然とした格差があるようにも思えるのだが。
しかし、勝敗は生きることに比べれば、オプションのようなものだ。
ミックが、若さを保つ秘訣だの成功の秘訣を聞かれるたびに、きっぱり「その日何がやれるかしか考えない」と答えていたのが印象的だ。
夫がストーンズファンなので、封切られたその日に観に行った。
マーティン・スコセッシが、ストーンズのわがままぶりに困惑するシーンから、映画が転がり出す。
直前まで、一曲目に何をやるのか教えてこない。こっちは、カメラ数十台でスタンバッテるのに。なに、そのライトで二〇秒も照らすとミック・ジャガーが燃える?そりゃまずいだろ……なんて、色々言っているスコセッシが映る。
あくまで導入部だ。それに、すべては、演出なのだ。
ミック・ジャガーのうごきは完璧。シルエットだけ見れば、二〇代の頃とほとんど変わらない。生き様がダンス化している。もしくは、ダンスが生き様化している。もう意味不明。ダンサーって、年をとらないんじゃないかと思ってしまう。
キースは、演奏の方も、好き放題、ルーズになっているような気がする。
ストーンズの世界に入っていくことは、確かに強い光に照らされ、おなじエネルギーを持って照らし返すことだ。上機嫌な、成功した、したたかな、時に悪魔的で神学的な、依然としてよくわからないロックそのものにまきこまれることだ。最後のサティスファクションが何から何まですごかった。
マーティン・スコセッシのインタビューから、この映画全体の言い表しがたいテーマがちょっと垣間みられた。というのは、スコセッシが数多くとって来たマフィアとストーンズとの共通性について聞かれた時、両者とも「僕が目撃し、経験し、理解しようとしていたことと大きく関係して」おり、タフであり、エッジもあり、美しくて正直で残酷だと答えたことだ。多分それ以上は言葉にできないような素材なのに違いない。
一ヶ月前に見た、ルー・リードの『ベルリン』もおなじくらいよかったけどね。
これはもしかたら眩しい友人たちへのやっかみであるばかりじゃなく、事実に近い現実をも言い表していたのかもしれない。私だって、嘘かまことか、「清志郎ですら食えてないらしい」とか凄い大御所が実は「金に汚い」とかよく聞かされたものだ。
近頃だって、贅沢の限りを尽くした小室哲哉が、いつの間にかまったく売れなくなって、詐欺でつかまってびっくりした。
音楽の世界における勝者が、どういう人たちのことなのかわからない。
しかし、ローリングストーンズを勝者と言わずして、誰を勝者と呼ぼうか。
ただし、曲の権利をすべて、ミックとキースが持っていることを考えれば、ストーンズというバンドの中にも、歴然とした格差があるようにも思えるのだが。
しかし、勝敗は生きることに比べれば、オプションのようなものだ。
ミックが、若さを保つ秘訣だの成功の秘訣を聞かれるたびに、きっぱり「その日何がやれるかしか考えない」と答えていたのが印象的だ。
夫がストーンズファンなので、封切られたその日に観に行った。
マーティン・スコセッシが、ストーンズのわがままぶりに困惑するシーンから、映画が転がり出す。
直前まで、一曲目に何をやるのか教えてこない。こっちは、カメラ数十台でスタンバッテるのに。なに、そのライトで二〇秒も照らすとミック・ジャガーが燃える?そりゃまずいだろ……なんて、色々言っているスコセッシが映る。
あくまで導入部だ。それに、すべては、演出なのだ。
ミック・ジャガーのうごきは完璧。シルエットだけ見れば、二〇代の頃とほとんど変わらない。生き様がダンス化している。もしくは、ダンスが生き様化している。もう意味不明。ダンサーって、年をとらないんじゃないかと思ってしまう。
キースは、演奏の方も、好き放題、ルーズになっているような気がする。
ストーンズの世界に入っていくことは、確かに強い光に照らされ、おなじエネルギーを持って照らし返すことだ。上機嫌な、成功した、したたかな、時に悪魔的で神学的な、依然としてよくわからないロックそのものにまきこまれることだ。最後のサティスファクションが何から何まですごかった。
マーティン・スコセッシのインタビューから、この映画全体の言い表しがたいテーマがちょっと垣間みられた。というのは、スコセッシが数多くとって来たマフィアとストーンズとの共通性について聞かれた時、両者とも「僕が目撃し、経験し、理解しようとしていたことと大きく関係して」おり、タフであり、エッジもあり、美しくて正直で残酷だと答えたことだ。多分それ以上は言葉にできないような素材なのに違いない。
一ヶ月前に見た、ルー・リードの『ベルリン』もおなじくらいよかったけどね。