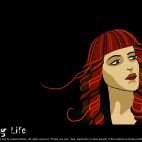フリー・ゾーン~明日が見える場所~ [DVD]
2009年2月7日 映画
カンヌ映画祭六十回記念作品『それぞれのシネマ』を見ていて、とても面白かったんだけど、とにかく三十三人の監督の三分の作品をつなげて見せているわけだから非常にめまぐるしい。しかも、映画内映画、スクリーン内スクリーン、劇場内劇場といった手法が多く見られて、そこに選ばれていない監督の作品(ゴダールとか)や映像(20世紀の記録映像とか)が映り込んで錯綜してる。
それでも、デヴィッド・リンチはいかにもそれらしい、とか、ダルデンヌ兄弟はやっぱり好き、とか、ロマン・ポランスキーはエッチだとかそれなりに納得する。
しかしこれだけ並べば、好き嫌いを越えて、なにか必然性を感じさせる映画といものが際立って浮かび上がってくるものじゃないだろうか。今回、私の場合は、アモス・ギタイにそれを感じた。それは、1930年代のワルシャワの映画館と現代のハイファの映画館の風景を(主に観客を)ゆっくり映し出した後に、その劇場の天井が爆撃で一瞬のうちに落ちて中で見ていた観客が犠牲になってしまう悲惨な映像。他にも暴力や戦争やを扱ったものはあったけど、なぜかギタイの作品が印象に残って、というかショックが残って、後で、2005年のギタイの『フリー・ゾーン』を借りて見た。
『フリーゾーン』は冒頭に、ナタリー・ポートマンが車の中で泣いてる長いシーンがあり、バックに長い長い歌(たぶんヘブライ語で)が歌われている。その長い長い歌の後、ナタリーポートマンがやっと泣き止んで、「この国を出なきゃ」と言い、映画の中の長い旅が始まる。すなわち、イスラエルからヨルダンへ、国境を超える長い旅である。しかし、その歌は、結局旅の果てに、最後にまた歌われてしまう。歌われること自体が、苦痛を伴う歌というのがあるのだ。とにかくなんか凄い歌だなと思い、記憶のために、ここに書いておくことにした。
「私の父が安く買った 子羊! 子羊!
私の父が安く買ったと そうハガダに書いてある
待ち伏せしていた猫が 子羊に跳びかかり 食い殺す
子羊を食い殺した猫を 犬が絞め殺す
私の父が安く買った 子羊!子羊!
そこに棍棒が現れて 罰に犬を激しく叩く
猫を食いちぎった犬を その猫は父が買った子羊を食い殺した猫
私の父が安く買った子羊!子羊!
火が棍棒を燃やす 犬を叩いた棒
猫を絞め殺した犬 子羊を食い殺した猫
私の父が安く買った子羊!子羊!
水が火を消す 棒を燃やした火 犬を叩いた棒
猫を絞め殺した犬 子羊を食い殺した猫
私の父が安く買った子羊!子羊!
近くを通った牛が火を消した水を飲む
火が棒を燃やす 棒が犬を叩き 犬が猫を絞め殺し
父が安く買った子羊を 猫が食い殺す
子羊!子羊!
水を飲んだ牛を殺しに肉屋がやってくる
火を消した水 棒を燃やした火 犬を罰した棒 猫を絞め殺した犬
父が買った子羊を食い殺した猫
堕天使が現れて肉屋を殺す
肉屋は水を飲んだ牛を殺し 水は火を消し 火は棒を燃やし 棒は犬をと叩き 犬は猫を絞め殺し猫が子羊を食い殺す
私の父が安く買った子羊!子羊!
なぜ歌うのか子羊よ
春はまだよ 過ぎ越の祭りも
いったい何が変わったの?
私は今年変わったわ
毎晩いつものように 同じ質問しかしなかった
今晩は 新しい質問がある
いつまでこの地獄が続くのか
今晩は新しい質問がある
いつまでこの地獄が続くのか
加害者から被害者へ 死刑執行人と犠牲者
狂気はいつまでつづくのか
いったいなにが変わったの?
私は今年変わったわ
私は優しい子羊だったけど
トラに 野生の狼に変わった
私は鳩 羚羊だったけど
今では何になったのかわからない
私の父が安く買った子羊!子羊!
私たちの父が安く買い
すべてが振り出しに戻る」
人によっては、暗号のように、歌詞の意味が分かってしまうかも知れないと思う。映画の中の女性たちが、「これはあくまで家族の問題」と言っていたのが印象的だった。今につながってしまう歌、すべてが振り出しに戻った今、真っ白なスクリーンに溶けていくナタリーポートマンと頭の中。
それでも、デヴィッド・リンチはいかにもそれらしい、とか、ダルデンヌ兄弟はやっぱり好き、とか、ロマン・ポランスキーはエッチだとかそれなりに納得する。
しかしこれだけ並べば、好き嫌いを越えて、なにか必然性を感じさせる映画といものが際立って浮かび上がってくるものじゃないだろうか。今回、私の場合は、アモス・ギタイにそれを感じた。それは、1930年代のワルシャワの映画館と現代のハイファの映画館の風景を(主に観客を)ゆっくり映し出した後に、その劇場の天井が爆撃で一瞬のうちに落ちて中で見ていた観客が犠牲になってしまう悲惨な映像。他にも暴力や戦争やを扱ったものはあったけど、なぜかギタイの作品が印象に残って、というかショックが残って、後で、2005年のギタイの『フリー・ゾーン』を借りて見た。
『フリーゾーン』は冒頭に、ナタリー・ポートマンが車の中で泣いてる長いシーンがあり、バックに長い長い歌(たぶんヘブライ語で)が歌われている。その長い長い歌の後、ナタリーポートマンがやっと泣き止んで、「この国を出なきゃ」と言い、映画の中の長い旅が始まる。すなわち、イスラエルからヨルダンへ、国境を超える長い旅である。しかし、その歌は、結局旅の果てに、最後にまた歌われてしまう。歌われること自体が、苦痛を伴う歌というのがあるのだ。とにかくなんか凄い歌だなと思い、記憶のために、ここに書いておくことにした。
「私の父が安く買った 子羊! 子羊!
私の父が安く買ったと そうハガダに書いてある
待ち伏せしていた猫が 子羊に跳びかかり 食い殺す
子羊を食い殺した猫を 犬が絞め殺す
私の父が安く買った 子羊!子羊!
そこに棍棒が現れて 罰に犬を激しく叩く
猫を食いちぎった犬を その猫は父が買った子羊を食い殺した猫
私の父が安く買った子羊!子羊!
火が棍棒を燃やす 犬を叩いた棒
猫を絞め殺した犬 子羊を食い殺した猫
私の父が安く買った子羊!子羊!
水が火を消す 棒を燃やした火 犬を叩いた棒
猫を絞め殺した犬 子羊を食い殺した猫
私の父が安く買った子羊!子羊!
近くを通った牛が火を消した水を飲む
火が棒を燃やす 棒が犬を叩き 犬が猫を絞め殺し
父が安く買った子羊を 猫が食い殺す
子羊!子羊!
水を飲んだ牛を殺しに肉屋がやってくる
火を消した水 棒を燃やした火 犬を罰した棒 猫を絞め殺した犬
父が買った子羊を食い殺した猫
堕天使が現れて肉屋を殺す
肉屋は水を飲んだ牛を殺し 水は火を消し 火は棒を燃やし 棒は犬をと叩き 犬は猫を絞め殺し猫が子羊を食い殺す
私の父が安く買った子羊!子羊!
なぜ歌うのか子羊よ
春はまだよ 過ぎ越の祭りも
いったい何が変わったの?
私は今年変わったわ
毎晩いつものように 同じ質問しかしなかった
今晩は 新しい質問がある
いつまでこの地獄が続くのか
今晩は新しい質問がある
いつまでこの地獄が続くのか
加害者から被害者へ 死刑執行人と犠牲者
狂気はいつまでつづくのか
いったいなにが変わったの?
私は今年変わったわ
私は優しい子羊だったけど
トラに 野生の狼に変わった
私は鳩 羚羊だったけど
今では何になったのかわからない
私の父が安く買った子羊!子羊!
私たちの父が安く買い
すべてが振り出しに戻る」
人によっては、暗号のように、歌詞の意味が分かってしまうかも知れないと思う。映画の中の女性たちが、「これはあくまで家族の問題」と言っていたのが印象的だった。今につながってしまう歌、すべてが振り出しに戻った今、真っ白なスクリーンに溶けていくナタリーポートマンと頭の中。
アッシャー家の末裔 (トールケース) [DVD]
2008年12月17日 映画
1928年に制作され、1997年に復元された、非常に美しく、非常に恐ろしい映画。
ルイス・ブニュエルが助監督。
シネフィルイマジカで放送されていたのを見たにすぎないけれど、呪われたフィルムのようで途中でやめられなかった。
その怖さは、他人の頭の中をのぞいているような不気味さ、本当に念写かなにかの形で露出してしまった誰かのヴィジョンを見せられている気味の悪さである。
言葉として「シニフェエなしのシニフィアン」という言い方があるけれど、この完成度の高い映画は、確かに、指示内容なしに成立する映像表現だと思う。しかし、物語である以上、何が起こったのか(行われたのか)把握できるはずなのに、この映画では本当に何が起こったのかがわからない。
だから隠されていることこそ本当におぞましいという感じで、このイメージを追っていったら……何が行われたのかという隠されていることのイメージを追っていったら、京極夏彦の『魍魎の匣(もうりょうのはこ)』みたいになるだろうなと思う。
映画になった『魍魎の匣(もうりょうのはこ)』は、去年のクリスマスイヴに見たのだが、つくづくクリスマスに見るような映画じゃなかったと見てから後悔したのだった。
ルイス・ブニュエルが助監督。
シネフィルイマジカで放送されていたのを見たにすぎないけれど、呪われたフィルムのようで途中でやめられなかった。
その怖さは、他人の頭の中をのぞいているような不気味さ、本当に念写かなにかの形で露出してしまった誰かのヴィジョンを見せられている気味の悪さである。
言葉として「シニフェエなしのシニフィアン」という言い方があるけれど、この完成度の高い映画は、確かに、指示内容なしに成立する映像表現だと思う。しかし、物語である以上、何が起こったのか(行われたのか)把握できるはずなのに、この映画では本当に何が起こったのかがわからない。
だから隠されていることこそ本当におぞましいという感じで、このイメージを追っていったら……何が行われたのかという隠されていることのイメージを追っていったら、京極夏彦の『魍魎の匣(もうりょうのはこ)』みたいになるだろうなと思う。
映画になった『魍魎の匣(もうりょうのはこ)』は、去年のクリスマスイヴに見たのだが、つくづくクリスマスに見るような映画じゃなかったと見てから後悔したのだった。
ディパーテッド (期間限定版) [DVD]
2008年12月16日 映画
『シャインアライト』は、スコセッシ映画の中で唯一「ギミー・シェルター」を使っていない映画だ、とミックジャガーがスコセッシに言ったそうだ。それでこれを見たくなった。ギミー・シェルターは冒頭から使われていた。映画の一音目として。ディカプリオが、『羊たちの沈黙』のジョディーフォスターと同じくらい、いい感じだった。
面白かった。
嘘には嘘を。真実には真実を。
嘘つきに真心を与えたり、真心に嘘を与えることは危険なことだ。
でもその危険は日常的なものだから、正体を隠しながら生きることが普通になる。
ナタリー・ポートマン役のアリスにしか共感はできないが、それは、アリスが愛を体現しているからだろう。
嘘が好きな人には嘘を与え、真実が好きな人には真実を与える。愛にとっては、嘘も真実も等価である。一枚の写真が嘘であっても真実であっても芸術であっても構わない。強制したりされないことが大事なのだ。例えば、自分は嘘が好きなくせに人には真実を強要するとか、自分は真実を語っているのだから人も真実を語るべきだとか、芸術を芸術として評価せよなどと要求しないことが肝要だ。愛というのは、実を言うと、固有の、自発的な人格であり、自由を創造しながら生きている。
愛を邪魔するのは裏切りではなくて憎しみなのだが、憎しみは自由を創造できなくなる状態のことなのだ。
アリスが、匿名の存在であることは象徴的だ。
彼女自身が悲しいストレンジャーだと言いたいのだろう。
嘘には嘘を。真実には真実を。
嘘つきに真心を与えたり、真心に嘘を与えることは危険なことだ。
でもその危険は日常的なものだから、正体を隠しながら生きることが普通になる。
ナタリー・ポートマン役のアリスにしか共感はできないが、それは、アリスが愛を体現しているからだろう。
嘘が好きな人には嘘を与え、真実が好きな人には真実を与える。愛にとっては、嘘も真実も等価である。一枚の写真が嘘であっても真実であっても芸術であっても構わない。強制したりされないことが大事なのだ。例えば、自分は嘘が好きなくせに人には真実を強要するとか、自分は真実を語っているのだから人も真実を語るべきだとか、芸術を芸術として評価せよなどと要求しないことが肝要だ。愛というのは、実を言うと、固有の、自発的な人格であり、自由を創造しながら生きている。
愛を邪魔するのは裏切りではなくて憎しみなのだが、憎しみは自由を創造できなくなる状態のことなのだ。
アリスが、匿名の存在であることは象徴的だ。
彼女自身が悲しいストレンジャーだと言いたいのだろう。
二日、やはり渋谷に見に行く。
見てよかった。
笑いどころは、いっぱいあったのに、なぜか観客はまったく笑わない。
ドゥ二・ラヴァン扮する緑の怪人メルドが、歯を叩きながら蚊が泣くような声で、メルド語で、「なぜ東京を爆撃したかと言えば、世界中の中で日本人が一番大嫌いだからだ。日本人ほど汚らわしい人たちはいない!」と訴えた時にも、会場は凍り付いたままだった。
あとで、夫に話して聞かせたら、お腹を抱えて笑っていたのに。
世界で最も清潔なんて言われてちょっといい気になっている私たちが、「世界で一番汚らわしい」なんて言われるなんて、ショッキングでありなんとも痛快ではなかろうか。
しかしあのトリロジーが私たち日本人にとって笑えない何かを突きつけていたのも事実な気がする。
一貫して語られる空洞化のイメージ。
逃れようのないアレゴリーとなった現実みたいなもの。
竹中直人が映画の役の中で「近頃じゃ誰も外に出てこない」という言葉が、単に物理的な引きこもりのことを言っているだけじゃない気がした。
見てよかった。
笑いどころは、いっぱいあったのに、なぜか観客はまったく笑わない。
ドゥ二・ラヴァン扮する緑の怪人メルドが、歯を叩きながら蚊が泣くような声で、メルド語で、「なぜ東京を爆撃したかと言えば、世界中の中で日本人が一番大嫌いだからだ。日本人ほど汚らわしい人たちはいない!」と訴えた時にも、会場は凍り付いたままだった。
あとで、夫に話して聞かせたら、お腹を抱えて笑っていたのに。
世界で最も清潔なんて言われてちょっといい気になっている私たちが、「世界で一番汚らわしい」なんて言われるなんて、ショッキングでありなんとも痛快ではなかろうか。
しかしあのトリロジーが私たち日本人にとって笑えない何かを突きつけていたのも事実な気がする。
一貫して語られる空洞化のイメージ。
逃れようのないアレゴリーとなった現実みたいなもの。
竹中直人が映画の役の中で「近頃じゃ誰も外に出てこない」という言葉が、単に物理的な引きこもりのことを言っているだけじゃない気がした。
タクシデルミア~ある剥製師の遺言~(初回限定版)
2008年9月29日 映画
鮮明に脳裏に焼き付いている映画だ。
パルフィ・ジョルジの前作『ハックル』は喜びに満ちて、どこまでも続く旅のようだった。
『タクシデルミア』の方は、途方もない大作で、苦渋に満ちた崇高な歴史物語だ。その道程には最高の到達点が用意されている。前人未踏のアートの完成。映画の巻末で語られるように、私たちは、「彼」のような芸術家をいまだかつて知らない。どのようにして彼が形成されてきたかを、映画によって垣間みるのみである。
新しい人間、先端の人間、人間を越える人間、それは家族の歴史の中でこそ語られるものなのかもしれないと思った。
パルフィ・ジョルジの前作『ハックル』は喜びに満ちて、どこまでも続く旅のようだった。
『タクシデルミア』の方は、途方もない大作で、苦渋に満ちた崇高な歴史物語だ。その道程には最高の到達点が用意されている。前人未踏のアートの完成。映画の巻末で語られるように、私たちは、「彼」のような芸術家をいまだかつて知らない。どのようにして彼が形成されてきたかを、映画によって垣間みるのみである。
新しい人間、先端の人間、人間を越える人間、それは家族の歴史の中でこそ語られるものなのかもしれないと思った。