『告白』といっても、殺意の告白である。殺したい相手への殺意の告白だ。そういう行為を、本当に、「告白」という日本語で言い表していいのだろうか。アウグスティヌスは、「自分に最も近いことはなにか」と自問自答しながら大著『告白』を書いたものだが、殺意の告白は「脅迫」って言わないか? それとも、殺意こそは、我々の「最も近いこと」になったのだろうか。
しかし、あまり、深刻なことを言わない方がいいだろう。これは、正真正銘のエンターテイメントなのだから。めくるめく「殺意」たちの繰り広げるショウである。読者は、あっというまに、「殺意」の暴露を楽しみ始める。
最初は、言葉が汚いなと漠然と感じる。『風花』の川上弘美の文章と比べると雲泥の差がある。
『風花』は、とにかく文章が素晴らしかった。読後一ヶ月目にしてようやく内容を自分がどう読んだか客観視できるが、読んだ当初は川上弘美の文章力にぼう然自失していた。一文一文の伝わりかたが半端じゃなかった。無駄な言葉がなく論理の飛躍もない文章、一分の隙もない。
「みっともないことなんだな、他人と共にやってゆこうと努力することって。
のゆりの鼻から、涙が出てくる。目からはほとんど出ず、鼻だけから、すうすうと流れ出てくる。ほんとうに、みっともないよね、わたし。つぶやきながら、のゆりは卓哉にぎゅっとかじりつく。卓哉の腕が少しだけあがって、のゆりの背中に、力なく、まわされる。」『風花』p.173
中盤の山場のシーンである。今読んでもどうしてこういう文章になるのか、はっきり思い出せる。一文一文が必然性を持っているからである。
『告白』は、逆に、論理の飛躍だらけ、言葉には「毒」を滲ませるための余計なノイズがいっぱいある。だから、文章が、荒れて汚く感じるのである。しかしそれらはすべて、意図されたものなのだ。
「馬鹿ですか? ラブレターの中には、散々、馬鹿という言葉が使われていました。あなたはいったい自分を何様だと思っているのでしょう。あなたがいったい何を生み出し、あなたが馬鹿と見下す人たちに、何の恩恵を与えているというのですか?」『告白』p.257
一番最後の章の最初の方の文章である。気持ちはわかるけど、特に必要な文とは思われない。特に「馬鹿ですか?」は、相手に「バカ!」と言っているのか、「バカって言いましたか?」と聞いているのかわからない。しかし、最後の章なので、論理より効果、ノイズを駆使して、渾身の一撃を加えなければならないのだろう。
ここにでてくる「告白者」数名は、ほぼ全員殺意の持ち主であり、殺人の実行犯である。殺意は、バトンリレーのように、告白者から告白者へと手渡されていく。殺意はミッションである。それゆえ、章のタイトルは、ミッションに生きる告白者を称して、「聖職者」「殉教者」「慈愛者」「信奉者」「伝道者」となっている。物語は、見事な円を描いて、最初の語り部のもとに戻ってくる。最後に、決定的な制裁が下される。完璧である。
でも私は、最後に、もう一章、「死者」の章がほしかったと思う。なぜなら、最後の文の論理の飛躍が許せなかったからである。
「ねえ、渡辺君。これが本当の復讐であり、あなたの更生の第一歩だとは思いませんか?」『告白』p.268
ネタばれになるが、これは、自分の子供を殺された女教師が、犯人の男子生徒の母親を殺すことによって、「復讐」を果たし、それが「更生」の第一歩だと言っている文だ。なぜ母親を殺すのかと言うと、こういう下りがある。
「あなたの気持ちは母親だけにしか向いていないのに、被害を被るのはいつも、母親以外の人物です。
あなたの世界に、あなたと愛するママしか存在しないのなら、ママを殺しなさい。」
きっとここで、大いに腑に落ちる人もいるだろうし、まったく腑に落ちない人もいるだろう。
これは、作家から読者への問いかけでもあるのだろう。私の願望にすぎないが、作家の本当の視座は、主人公「子供を殺された女教師」ではなく、この作品の中で唯一、殺意の告白者ではない本当の告白者「母を弟に殺された姉」「被害者と加害者両方の家族」にある、と感じる。一瞬しか出てこないが、その身を縮めて書いているさまが、本当の「はじまり」という気がした。
だとしたら、なおさら、「はじまり」に対する「終わり」がないような気がする。収まりを付けたいので、私が勝手に書いておきます。
「死者
私は読者という死者です。あなたの告白によって何度も殺されました。そうです。牛乳に混入された毒で殺されたのでもなく、大学にしかけられた爆薬で殺されたのでもありません。読むという行為によって殺されたのです。
事実、告白者の一人か二人、もしかしたら全員が、手を下すことによってではなく、言葉によって人を殺したのです。悪意のある言葉、相手になんとか打撃を与えようとする言葉によって殺されたのです。
でも、安心して下さい。本当の死者は、こんな風に語ったりしませんから。
無惨に死んだ私のために、死んでくれだの、復讐してくれだの、言いません。
死者は黙して語らず、これが原則です。死者は戻ってこないし、語ったりもしません。だから、死者のために復讐するのは、死者のためでなく、生者のためです。
生者が、自分の中のまだ死んでいない死者たちの言葉を聞いて、さぞ悔しかろう、さぞ無念だったろうと心を痛めてくれるのです。
しかし、残念ながら、死者の死はそんなものではありません。容赦のないものです。私には、死が生者の問題を解決するとは思えません。死は、生きるものにとっては、謎そのものではないでしょうか。なぜ、生者は、謎の方向へ、解決を求めるのでしょうか。自分たちのわかる限りの方向へ、解決を押し進めないのでしょうか。なぜ、死が、「更生の第一歩」なのでしょうか。
他者に、ただ痛みを与えたい。なぜなら、痛みを覚えたから。告白者たちが言っていることはそういうことです。彼らにとって、おのれの不幸こそは正義なのです。正義を通すためには、相手に不幸を与える必要があるのです。死者には関係がありません。痛みとともに死んだのですから。」
しかし、あまり、深刻なことを言わない方がいいだろう。これは、正真正銘のエンターテイメントなのだから。めくるめく「殺意」たちの繰り広げるショウである。読者は、あっというまに、「殺意」の暴露を楽しみ始める。
最初は、言葉が汚いなと漠然と感じる。『風花』の川上弘美の文章と比べると雲泥の差がある。
『風花』は、とにかく文章が素晴らしかった。読後一ヶ月目にしてようやく内容を自分がどう読んだか客観視できるが、読んだ当初は川上弘美の文章力にぼう然自失していた。一文一文の伝わりかたが半端じゃなかった。無駄な言葉がなく論理の飛躍もない文章、一分の隙もない。
「みっともないことなんだな、他人と共にやってゆこうと努力することって。
のゆりの鼻から、涙が出てくる。目からはほとんど出ず、鼻だけから、すうすうと流れ出てくる。ほんとうに、みっともないよね、わたし。つぶやきながら、のゆりは卓哉にぎゅっとかじりつく。卓哉の腕が少しだけあがって、のゆりの背中に、力なく、まわされる。」『風花』p.173
中盤の山場のシーンである。今読んでもどうしてこういう文章になるのか、はっきり思い出せる。一文一文が必然性を持っているからである。
『告白』は、逆に、論理の飛躍だらけ、言葉には「毒」を滲ませるための余計なノイズがいっぱいある。だから、文章が、荒れて汚く感じるのである。しかしそれらはすべて、意図されたものなのだ。
「馬鹿ですか? ラブレターの中には、散々、馬鹿という言葉が使われていました。あなたはいったい自分を何様だと思っているのでしょう。あなたがいったい何を生み出し、あなたが馬鹿と見下す人たちに、何の恩恵を与えているというのですか?」『告白』p.257
一番最後の章の最初の方の文章である。気持ちはわかるけど、特に必要な文とは思われない。特に「馬鹿ですか?」は、相手に「バカ!」と言っているのか、「バカって言いましたか?」と聞いているのかわからない。しかし、最後の章なので、論理より効果、ノイズを駆使して、渾身の一撃を加えなければならないのだろう。
ここにでてくる「告白者」数名は、ほぼ全員殺意の持ち主であり、殺人の実行犯である。殺意は、バトンリレーのように、告白者から告白者へと手渡されていく。殺意はミッションである。それゆえ、章のタイトルは、ミッションに生きる告白者を称して、「聖職者」「殉教者」「慈愛者」「信奉者」「伝道者」となっている。物語は、見事な円を描いて、最初の語り部のもとに戻ってくる。最後に、決定的な制裁が下される。完璧である。
でも私は、最後に、もう一章、「死者」の章がほしかったと思う。なぜなら、最後の文の論理の飛躍が許せなかったからである。
「ねえ、渡辺君。これが本当の復讐であり、あなたの更生の第一歩だとは思いませんか?」『告白』p.268
ネタばれになるが、これは、自分の子供を殺された女教師が、犯人の男子生徒の母親を殺すことによって、「復讐」を果たし、それが「更生」の第一歩だと言っている文だ。なぜ母親を殺すのかと言うと、こういう下りがある。
「あなたの気持ちは母親だけにしか向いていないのに、被害を被るのはいつも、母親以外の人物です。
あなたの世界に、あなたと愛するママしか存在しないのなら、ママを殺しなさい。」
きっとここで、大いに腑に落ちる人もいるだろうし、まったく腑に落ちない人もいるだろう。
これは、作家から読者への問いかけでもあるのだろう。私の願望にすぎないが、作家の本当の視座は、主人公「子供を殺された女教師」ではなく、この作品の中で唯一、殺意の告白者ではない本当の告白者「母を弟に殺された姉」「被害者と加害者両方の家族」にある、と感じる。一瞬しか出てこないが、その身を縮めて書いているさまが、本当の「はじまり」という気がした。
だとしたら、なおさら、「はじまり」に対する「終わり」がないような気がする。収まりを付けたいので、私が勝手に書いておきます。
「死者
私は読者という死者です。あなたの告白によって何度も殺されました。そうです。牛乳に混入された毒で殺されたのでもなく、大学にしかけられた爆薬で殺されたのでもありません。読むという行為によって殺されたのです。
事実、告白者の一人か二人、もしかしたら全員が、手を下すことによってではなく、言葉によって人を殺したのです。悪意のある言葉、相手になんとか打撃を与えようとする言葉によって殺されたのです。
でも、安心して下さい。本当の死者は、こんな風に語ったりしませんから。
無惨に死んだ私のために、死んでくれだの、復讐してくれだの、言いません。
死者は黙して語らず、これが原則です。死者は戻ってこないし、語ったりもしません。だから、死者のために復讐するのは、死者のためでなく、生者のためです。
生者が、自分の中のまだ死んでいない死者たちの言葉を聞いて、さぞ悔しかろう、さぞ無念だったろうと心を痛めてくれるのです。
しかし、残念ながら、死者の死はそんなものではありません。容赦のないものです。私には、死が生者の問題を解決するとは思えません。死は、生きるものにとっては、謎そのものではないでしょうか。なぜ、生者は、謎の方向へ、解決を求めるのでしょうか。自分たちのわかる限りの方向へ、解決を押し進めないのでしょうか。なぜ、死が、「更生の第一歩」なのでしょうか。
他者に、ただ痛みを与えたい。なぜなら、痛みを覚えたから。告白者たちが言っていることはそういうことです。彼らにとって、おのれの不幸こそは正義なのです。正義を通すためには、相手に不幸を与える必要があるのです。死者には関係がありません。痛みとともに死んだのですから。」

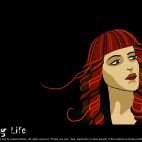
コメント