徐京植 多和田葉子『ソウルーベルリン 玉突き書簡』
2009年6月18日 読書岩波書店 2008.4
徐京植は1951年京都生まれ、韓国滞在中の在日朝鮮人二世作家。
多和田葉子は1960年東京生まれ、ベルリン在住の作家。
2007.2から2007.11までに交わされた二人の書簡集がこの『ソウルーベルリン 玉突き書簡』だ。
とてもおもしろかった。一信ごとにテーマが生まれ、十のテーマをめぐり、二十回の手紙のやり取り。読者は、多和田葉子の記述の中で、世界の変貌を目の当たりにし、意識がわあっとそれこそ高速で開けていくのを感じるのではないか。一方、徐京植の記述からは、私たちがそこにはまりこんでいまだに逃れられないでいる歴史の癒しがたい傷の深さを思い出すのだと思う。私自身は、多和田葉子にずいぶん救われる思いがした。昔、ここでブログを別のタイトル別の名前でやっていたとき、相互リンクの方に「あなたは、多和田葉子を参考にするといいんじゃないか」と言っていただいたのだが、私はそのときは多和田葉子の良さがわからず、せっかく薦めてくれた彼にとても失礼をしてしまったと思う。今では、本当にその時のこと、その人に感謝している。
本のことに戻ると、十章あるうちのすべての章(信)ごとに、抜き書きしたい文章があり、また関係なく見えるすべてのテーマが、深く結びついている。
一番重いテーマは、やはり日本の自殺率の高さに触れている第九信の「殉教」だろう。
ヨーロッパでは、イスラム原理主義者による自爆テロが起こるたびに、日本の「カミカゼ」特攻隊が引き合いに出され、「不可解な不気味なオリエント」という安易な括られかたをしてしまい、しかも日本には「死を賞賛する文化」があるという認識が定着しているという。
「イスラム教自体はキリスト教と同じで、決して自殺賞賛などしていません。だから、テロリストは日本にヒントを得たという仮説が出るのも無理はないわけです。去年ヨルダンに行った時に、日本の特攻精神を褒めたたえたアラビア語の詩を見せてもらい、ぎょっとしました。なぜ死を賞賛する文化がうまれてしまったのかを世界に向かって説明する責任が今新たにうまれて来ている気がするのです。」p.140
このことは、今の日本の自殺率の高さや、いじめられている子供の「親や先生に話すくらいなら死んだ方がまし」という気持ちや、「死んで尊厳を守る」という考え方、「死んで責任を取る」という態度、「死ぬ覚悟でやっている」というような言い方、武士の切腹、三島の美学、「特攻隊はお国のために自分の意志で死んでいった」かのような言説のすべてにつながっていく話で、よくよく考えてみれば、まったく他人事ではなかった。
私の父は今でも「国のために命を捧げるのは当然だろ」としきりに言いたがることがあるし、母は「老醜をさらすくらいなら早く死んだ方がまし」とすごく若いときから言い続けて、本当に若死にしてしまったという経緯がある。私は、そういう両親の言語から身を守るために自分の意志でキリスト教に入信したり、学問的な論理的な言語体系で心を武装しようとした時もあったくらいなのだ。
ただ、両親の名誉のために言うなら、彼らが、キリスト教の悪口を言いながらも娘を幼児のときからミッション系の学校に通わせ、大人になると学問をはじめてかわいげがなくなっていくことにいやいやながらもどこか安堵して見守っていたのはたぶん事実であって、結局、父や母の死生観は、本音ではなく、どこか演技としての要素があったのではないかと思う。
これは、日本の「死を賞賛する文化」の中の、死を演劇的なものにして人生そのものを舞台にしたいという根深い欲求を、私の父も母もどこかで植え付けられていたけれど、でも本質的なところではそれに抗っていたということなのだと思う。
「自殺とは、誇りを持って、あるいは絶望して、あるいは虚無感に身を任せて、個人が命を断つということではないようです。自殺は生というよりは性の表現形態の一つで、演劇的要素が強く、個人ではなく複数の人間のできごとであるということです。みんなに殺されると言っていいかもしれません。」p.138
これをルネジラールなら、人間の人間化の過程にあった「一体全員の暴力」と呼ぶだろう。それはいまだに繰り返され、文化によっては賞賛されることさえあり、日本の文化にはその傾向があるということかもしれない。
だけど、自殺をいかなる意味でも賞賛しない立場からすれば、それこそは野蛮、動物や野性回帰するのとは逆方向の、人間にしかない野蛮である。そう感じる人は、なんとしてもそれを阻止しなければならないと感じ、自分の出来るやり方で自殺を阻止しようとする。そこには膨大なエネルギ−が投入されることになる。
私は、そんな多くの人々を敗北させる演劇的な死よりも、動物的な死の方が、美しさの点ではるかに勝っていると思う。
徐京植は、金子文子の死を挙げて、それが「国家」から「性愛」を取り戻す死だったとしている。だけど、それは、英雄的な死を特権化して、一般的な自殺をとるにたらないものとするハイデッガー的な考え方に似てしまう。
また、彼は、自殺をなくすためには「生きやすい世の中にすること」と言うが(もちろん制度はどうにかしなければならないが)、そんなことより、もしかしたら、「演劇的な死に方につながる演劇的な生き方をやめる」という方向転換が一番必要なのではないかと思ってしまう。美学の転換である。
否応もなく人間である野蛮を昇華させるために、演劇そのものや諸々の芸術のジャンルがあるのに、なぜ、わざわざ演劇的な生き方や死に方をする必要があるのだろう。
私の母も、そういう生き方をもう少し早くにやめていたらもっと長く生きて、もっと話し合えたろうにと思う。悪口を言う人はいるかもしれないけれど、演劇な生き方をやめるのを本気で止める人はいない、と思う。むしろだれもが、そこから降りたがっているのではないだろうか。美学はその外部が見えなければ恐ろしいものだ。死を賞賛する文化を支えている美学は操作かもしれないのに、それに気づくことさえないのだから残酷である。
徐京植は1951年京都生まれ、韓国滞在中の在日朝鮮人二世作家。
多和田葉子は1960年東京生まれ、ベルリン在住の作家。
2007.2から2007.11までに交わされた二人の書簡集がこの『ソウルーベルリン 玉突き書簡』だ。
とてもおもしろかった。一信ごとにテーマが生まれ、十のテーマをめぐり、二十回の手紙のやり取り。読者は、多和田葉子の記述の中で、世界の変貌を目の当たりにし、意識がわあっとそれこそ高速で開けていくのを感じるのではないか。一方、徐京植の記述からは、私たちがそこにはまりこんでいまだに逃れられないでいる歴史の癒しがたい傷の深さを思い出すのだと思う。私自身は、多和田葉子にずいぶん救われる思いがした。昔、ここでブログを別のタイトル別の名前でやっていたとき、相互リンクの方に「あなたは、多和田葉子を参考にするといいんじゃないか」と言っていただいたのだが、私はそのときは多和田葉子の良さがわからず、せっかく薦めてくれた彼にとても失礼をしてしまったと思う。今では、本当にその時のこと、その人に感謝している。
本のことに戻ると、十章あるうちのすべての章(信)ごとに、抜き書きしたい文章があり、また関係なく見えるすべてのテーマが、深く結びついている。
一番重いテーマは、やはり日本の自殺率の高さに触れている第九信の「殉教」だろう。
ヨーロッパでは、イスラム原理主義者による自爆テロが起こるたびに、日本の「カミカゼ」特攻隊が引き合いに出され、「不可解な不気味なオリエント」という安易な括られかたをしてしまい、しかも日本には「死を賞賛する文化」があるという認識が定着しているという。
「イスラム教自体はキリスト教と同じで、決して自殺賞賛などしていません。だから、テロリストは日本にヒントを得たという仮説が出るのも無理はないわけです。去年ヨルダンに行った時に、日本の特攻精神を褒めたたえたアラビア語の詩を見せてもらい、ぎょっとしました。なぜ死を賞賛する文化がうまれてしまったのかを世界に向かって説明する責任が今新たにうまれて来ている気がするのです。」p.140
このことは、今の日本の自殺率の高さや、いじめられている子供の「親や先生に話すくらいなら死んだ方がまし」という気持ちや、「死んで尊厳を守る」という考え方、「死んで責任を取る」という態度、「死ぬ覚悟でやっている」というような言い方、武士の切腹、三島の美学、「特攻隊はお国のために自分の意志で死んでいった」かのような言説のすべてにつながっていく話で、よくよく考えてみれば、まったく他人事ではなかった。
私の父は今でも「国のために命を捧げるのは当然だろ」としきりに言いたがることがあるし、母は「老醜をさらすくらいなら早く死んだ方がまし」とすごく若いときから言い続けて、本当に若死にしてしまったという経緯がある。私は、そういう両親の言語から身を守るために自分の意志でキリスト教に入信したり、学問的な論理的な言語体系で心を武装しようとした時もあったくらいなのだ。
ただ、両親の名誉のために言うなら、彼らが、キリスト教の悪口を言いながらも娘を幼児のときからミッション系の学校に通わせ、大人になると学問をはじめてかわいげがなくなっていくことにいやいやながらもどこか安堵して見守っていたのはたぶん事実であって、結局、父や母の死生観は、本音ではなく、どこか演技としての要素があったのではないかと思う。
これは、日本の「死を賞賛する文化」の中の、死を演劇的なものにして人生そのものを舞台にしたいという根深い欲求を、私の父も母もどこかで植え付けられていたけれど、でも本質的なところではそれに抗っていたということなのだと思う。
「自殺とは、誇りを持って、あるいは絶望して、あるいは虚無感に身を任せて、個人が命を断つということではないようです。自殺は生というよりは性の表現形態の一つで、演劇的要素が強く、個人ではなく複数の人間のできごとであるということです。みんなに殺されると言っていいかもしれません。」p.138
これをルネジラールなら、人間の人間化の過程にあった「一体全員の暴力」と呼ぶだろう。それはいまだに繰り返され、文化によっては賞賛されることさえあり、日本の文化にはその傾向があるということかもしれない。
だけど、自殺をいかなる意味でも賞賛しない立場からすれば、それこそは野蛮、動物や野性回帰するのとは逆方向の、人間にしかない野蛮である。そう感じる人は、なんとしてもそれを阻止しなければならないと感じ、自分の出来るやり方で自殺を阻止しようとする。そこには膨大なエネルギ−が投入されることになる。
私は、そんな多くの人々を敗北させる演劇的な死よりも、動物的な死の方が、美しさの点ではるかに勝っていると思う。
徐京植は、金子文子の死を挙げて、それが「国家」から「性愛」を取り戻す死だったとしている。だけど、それは、英雄的な死を特権化して、一般的な自殺をとるにたらないものとするハイデッガー的な考え方に似てしまう。
また、彼は、自殺をなくすためには「生きやすい世の中にすること」と言うが(もちろん制度はどうにかしなければならないが)、そんなことより、もしかしたら、「演劇的な死に方につながる演劇的な生き方をやめる」という方向転換が一番必要なのではないかと思ってしまう。美学の転換である。
否応もなく人間である野蛮を昇華させるために、演劇そのものや諸々の芸術のジャンルがあるのに、なぜ、わざわざ演劇的な生き方や死に方をする必要があるのだろう。
私の母も、そういう生き方をもう少し早くにやめていたらもっと長く生きて、もっと話し合えたろうにと思う。悪口を言う人はいるかもしれないけれど、演劇な生き方をやめるのを本気で止める人はいない、と思う。むしろだれもが、そこから降りたがっているのではないだろうか。美学はその外部が見えなければ恐ろしいものだ。死を賞賛する文化を支えている美学は操作かもしれないのに、それに気づくことさえないのだから残酷である。
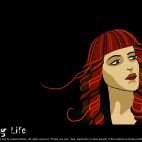
コメント