またもや夜中にミルクを飲んでいる。
本当は、この本の感想を書くつもりはなかった。
本当は、伊藤整の『街と村 生物祭 イカルス失墜』(講談社文藝文庫, 1993)の感想を書きたいのである。でも、写真がないから、この本の表紙で繋ぎ止めよう。
『樹液そして果実』には、伊藤整についての短い文章がある。
それによると、伊藤整と言えば『小説の方法』だが、「『小説の方法』の最も重要な基盤は、日本文化とギリシア文化との相似といふとらへ方である。両者はいづれもキリスト教の戒律と無縁であつたから、たとへばホメロスのやうに、たとへば徳田秋聲のやうに、エゴをむきだしに提出して、人間性への残酷な認識に到達することができたと伊藤は考へていたらしい」とあり、なるほどと思う。もしかしたら、ギリシア悲劇やプラトン以前のギリシア的思考を想起したニーチェのような、木田元のようなことを考えていたのかもしれないと思い、腑に落ちるところがあった。
丸谷才一は、しかし、伊藤整は評論家としては、西洋十九世紀のリアリズム文学の宣言を真に受けた近代日本文学の伝統にずいぶん忠実であって、小説家としても「ずいぶん無理して」いたのではないかと言っている。
でも、小説家としての伊藤整の真価は、そういうところにあるのだろうかと疑問に思う。
私は、『街と村 生物祭 イカルス失墜』と読んで、伊藤整は、西洋近代の自然科学的自然観みたいなものに照らされない〈暗がり〉を作品の中に保持し得た作家だと思った。 その暗がりは、本当に日本的なものであって、〈近代の光〉に照らし出されたあらゆる小説には決して読み取れないような暗さ、言語に住まう自然なのである。「街と村」の特に「幽鬼の村」では、主人公は、生者であると同時に死者であり、そこにいると同時に不在であり、私小説であるにもかかわらず不思議なことに人間のいない植物だけの時空間が立ち現れ、植物達が語りだしたりする。宗教であれ、学問であれ、文学であれ、イデオロギーであれ、日本人のどうしようもない土着性とその滑稽さは拭いがたいほどの濃密な自然であるという気がした。痛々しいほど克明な内面の描写さえも、関東大震災後の昭和、のっぺりした不安な時代を生きる自己を全身記号と化して書いているようなそんな執念を感じるのだが、その体験は作家の身体という暗がりへの接触であると思う。
自然は、私達の中にあるのか、外にあるのか、私達は、その一部なのか、それとも絶対的な他者なのか、3.11以来ずっと心にある問いである。
余談だけれど、『街と村 生物祭 イカルス失墜』に収録されている中で、一番好きだったのは、「石狩」という短編で、父の死後、歌子という狂女を追い求めて石狩に旅に出た主人公が汽車の中で、胡散臭い宗教家の胡散臭い因縁話を端で聞いているうちに滝のように涙をこぼしてしまい、しまいに「莫迦野郎!」「俺のことは君の説教に関係がないんだ」と、仁王立ちで大声を張り上げ、怒りを爆発させ、車内で注目を浴びてしまう箇所がやたら好きだった。伊藤整、面白い。
本当は、この本の感想を書くつもりはなかった。
本当は、伊藤整の『街と村 生物祭 イカルス失墜』(講談社文藝文庫, 1993)の感想を書きたいのである。でも、写真がないから、この本の表紙で繋ぎ止めよう。
『樹液そして果実』には、伊藤整についての短い文章がある。
それによると、伊藤整と言えば『小説の方法』だが、「『小説の方法』の最も重要な基盤は、日本文化とギリシア文化との相似といふとらへ方である。両者はいづれもキリスト教の戒律と無縁であつたから、たとへばホメロスのやうに、たとへば徳田秋聲のやうに、エゴをむきだしに提出して、人間性への残酷な認識に到達することができたと伊藤は考へていたらしい」とあり、なるほどと思う。もしかしたら、ギリシア悲劇やプラトン以前のギリシア的思考を想起したニーチェのような、木田元のようなことを考えていたのかもしれないと思い、腑に落ちるところがあった。
丸谷才一は、しかし、伊藤整は評論家としては、西洋十九世紀のリアリズム文学の宣言を真に受けた近代日本文学の伝統にずいぶん忠実であって、小説家としても「ずいぶん無理して」いたのではないかと言っている。
でも、小説家としての伊藤整の真価は、そういうところにあるのだろうかと疑問に思う。
私は、『街と村 生物祭 イカルス失墜』と読んで、伊藤整は、西洋近代の自然科学的自然観みたいなものに照らされない〈暗がり〉を作品の中に保持し得た作家だと思った。 その暗がりは、本当に日本的なものであって、〈近代の光〉に照らし出されたあらゆる小説には決して読み取れないような暗さ、言語に住まう自然なのである。「街と村」の特に「幽鬼の村」では、主人公は、生者であると同時に死者であり、そこにいると同時に不在であり、私小説であるにもかかわらず不思議なことに人間のいない植物だけの時空間が立ち現れ、植物達が語りだしたりする。宗教であれ、学問であれ、文学であれ、イデオロギーであれ、日本人のどうしようもない土着性とその滑稽さは拭いがたいほどの濃密な自然であるという気がした。痛々しいほど克明な内面の描写さえも、関東大震災後の昭和、のっぺりした不安な時代を生きる自己を全身記号と化して書いているようなそんな執念を感じるのだが、その体験は作家の身体という暗がりへの接触であると思う。
自然は、私達の中にあるのか、外にあるのか、私達は、その一部なのか、それとも絶対的な他者なのか、3.11以来ずっと心にある問いである。
余談だけれど、『街と村 生物祭 イカルス失墜』に収録されている中で、一番好きだったのは、「石狩」という短編で、父の死後、歌子という狂女を追い求めて石狩に旅に出た主人公が汽車の中で、胡散臭い宗教家の胡散臭い因縁話を端で聞いているうちに滝のように涙をこぼしてしまい、しまいに「莫迦野郎!」「俺のことは君の説教に関係がないんだ」と、仁王立ちで大声を張り上げ、怒りを爆発させ、車内で注目を浴びてしまう箇所がやたら好きだった。伊藤整、面白い。

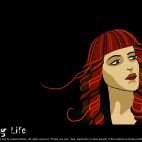
コメント